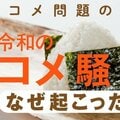米が高いのは中間業者や転売ヤーのせい――。そう考えている消費者も少なくないのではないか。小泉進次郎農林水産相までが米の流通実態を「不透明」「ブラックボックス」と問題視、実態の解明に向け調査を実施している。だが、流通現場からは「根本の原因はまったく別だ」との声が上がる。
* * *
米が高いのは米不足だから
「なぜ、米が高いのか? 米不足が根本の原因ですよ」
東京近郊の老舗米店の店主、中村真一さん(仮名)は、そう話す。
「今、政府は小売業者などの米の在庫量を2年前にさかのぼって調べている。『流通の目詰まりはここで起きている。この業者が米の価格をつり上げている』と言いたいのでしょうけれど、矛先が違うとしか思えない」(中村さん)
米が高いのは、米が不足しているから――。記者は昨年来、さまざまな米の関係者に取材を重ねてきたが、これ以外の答えを聞いたことがない。ただひとつ、農林水産省を除いては。
小泉農水相「流通はブラックボックス」
これまで小泉農水相は、米の流通について、「5次卸とか5次問屋とかあまりにも多い」(6月1日)、「『他の食料品に比べ、米の流通は極めて複雑怪奇、ブラックボックス』と指摘が寄せられている」(6月5日)などと発言してきた。6月17日には、国に届け出ているすべての米の出荷・販売業者に対して、6月末時点の在庫量の報告を求める調査を実施すると発表した。調査結果は7月下旬に公表される予定だ。
大手スーパーの価格形成力
しかし、中村さんの目には、この調査はあまり意味のないものに映る。現在、米の購入先として圧倒的なシェア55.8%を持つのはスーパー(今年5月、米穀安定供給確保支援機構調べ)だ。特に大手スーパーは消費者米価の価格形成力を握る。
「原価管理の厳しい大手スーパーの流通に、中間マージンで儲ける中小の卸や問屋が入る隙間は全くない。入ろうとしても無理ですよ」(中村さん)
中間業者を排す動きは米店でも広がっている。中村さんはその先駆者で、20年ほど前から農家との直接取引を増やしてきた。倉庫にはその米が保管されているが、それは今年の新米が入荷するまで継続的に販売するためのストックで、「買い占めているわけではない」と説明する。
「結局、国は『流通業者が悪者』ということにしたいのでしょう」(中村さん)