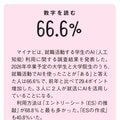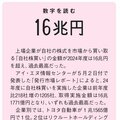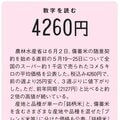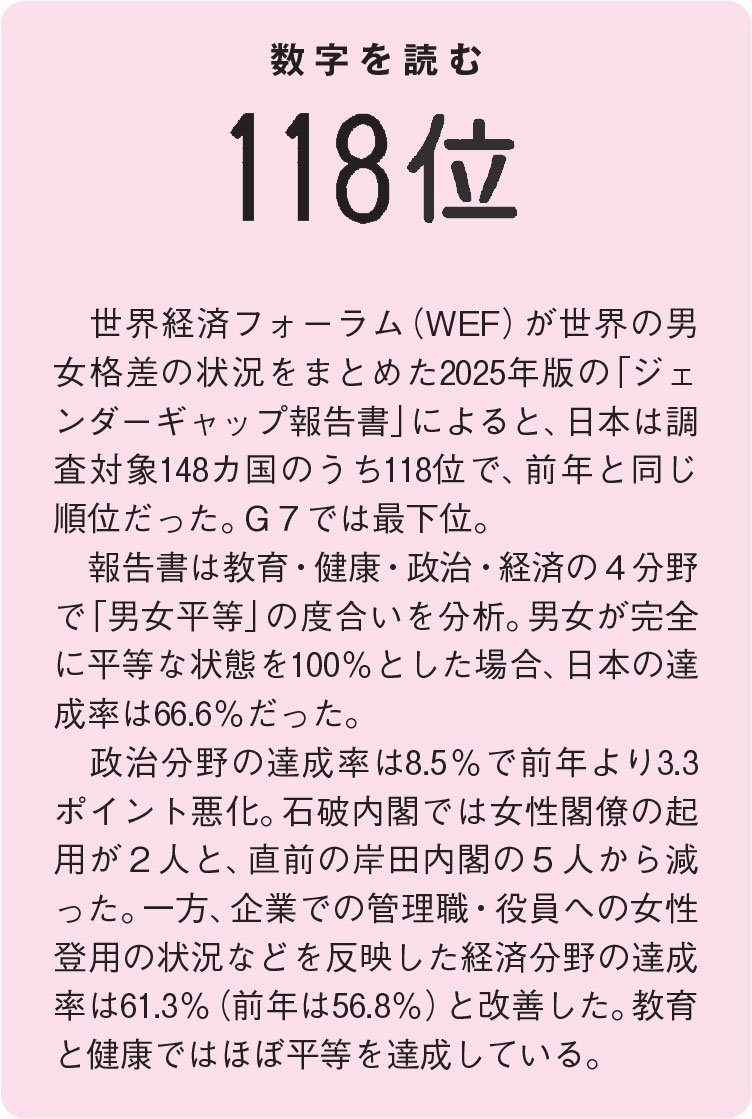
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年7月7日号より。
* * *
本を読んでいて、強烈な違和感を覚えた経済学者の話があった。朝日新聞取材班がまとめた『8がけ社会』という本では、現在の日本社会で進んでいる人手不足の問題に警鐘を鳴らしている。
生産年齢人口が2040年には現在の8割に減ってしまい社会基盤が崩れるという問題提起だが、その中である経済学者が妙に楽観的な見方を示している。彼は、賃金が上がれば高齢者や女性が働くようになるから問題ないというのだ。
まるで女性がまだ十分に働いていない存在かのように語るこの視点には、明らかな誤解がある。彼の目には、賃金の発生しない家事や育児が「労働」として映っていないのだろう。
先日発表された世界経済フォーラム(WEF)のジェンダーギャップ指数では、日本はG7(主要7カ国)で最下位、世界148カ国中118位という低迷ぶりだった。政治分野に次いで経済分野のギャップが大きいそうだ。管理職比率や賃金格差など、改善が見られない項目が多く、日本社会の男女格差が深刻であることが改めて浮き彫りとなった。
ひきつづき「女性が活躍できる社会」を目指していくのは、日本にとって大事なことだろう。しかし、冒頭の経済学者のように、女性を単に「労働市場の潜在的リソース」とみなすような視点では、さらなる負担を女性に押しつけるだけになる。こうした議論で見落とされがちなのは、膨大な無償労働である家事や育児のことだ。
たとえば、6歳未満の子どもがいる家庭で女性が家事や育児に費やす時間は1日平均7時間28分に達する(内閣府男女共同参画局による調査)。一方、男性は1時間54分にとどまる。
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどでも女性が費やす時間が長い傾向があるが、それでも男女の差は3時間程度だ。日本はその約2倍にあたる5時間半の差がある。この差が毎日積み重なれば、女性が背負う負担は計り知れない。