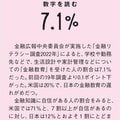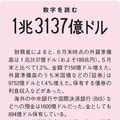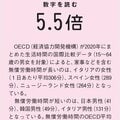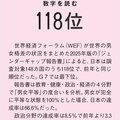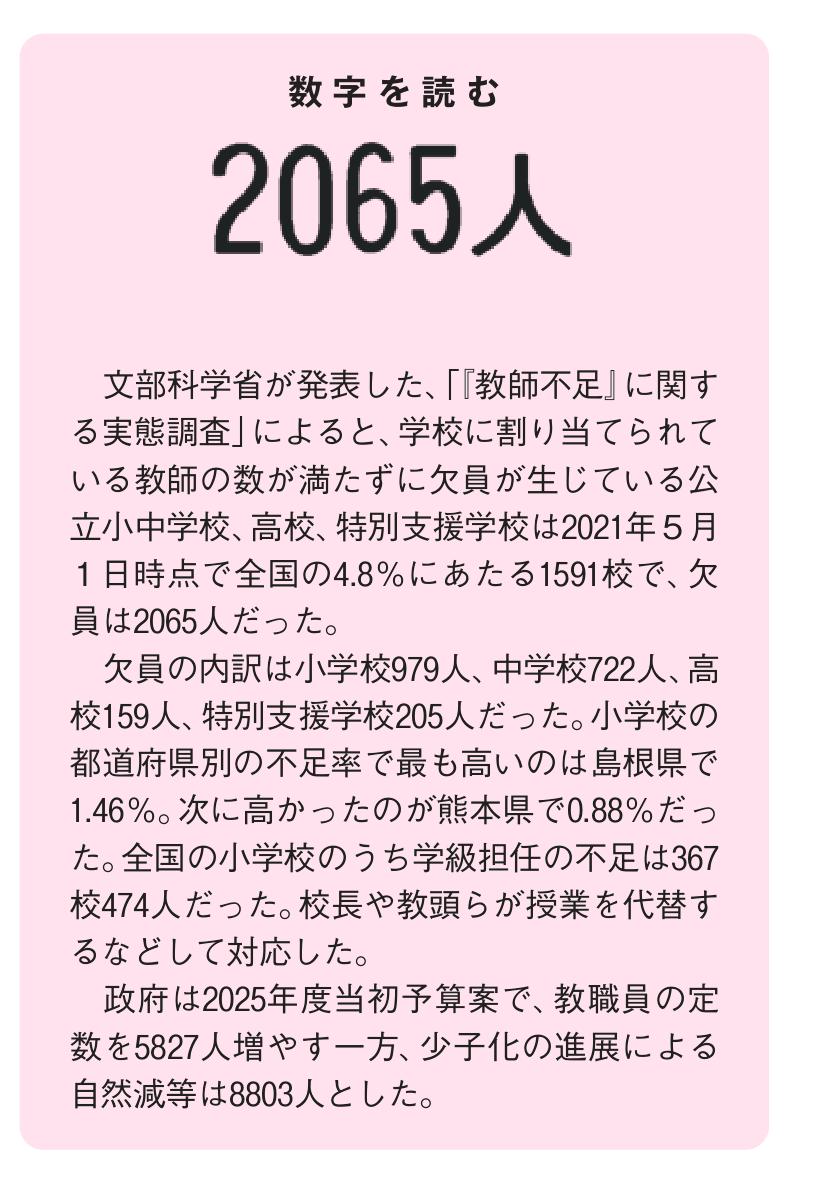
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年2月24日号より。
* * *
いまの日本で、投資すべきことはなんだろうか?
先日、熊本へ行く機会があった。熊本といえば、世界的な半導体メーカーの台湾積体電路製造(TSMC)の進出で大きな注目を集めている。とはいえ、僕が熊本を訪れたのはTSMCの工場視察が目的ではなく、「Kumamoto Education Week」という教育イベントで、お金の教育について市内の高校生に話すためだった。
イベントでは多くの教育関係者と会うことができ、その中で「教員不足」の問題が深刻だという話を聞いた。熊本県は、全国的に見ても教員の充足率がかなり低いらしい。今年度は教員が集まらず、2回もの追加募集を行ったという。特に英語の先生が足りないそうだ。
これはTSMCの進出による人材争奪戦が一因だという。地元企業や銀行なども新人採用を強化し、初任給を5万円近く引き上げる動きが出ているのだそうだ。もともと銀行などの初任給は、学校の先生と大差なかった。ところが大幅に上がった結果、若い人材が企業に流れやすくなり、教員になる人がいっそう減ってしまっているらしい。TSMC誘致そのものは経済的には良い話なのだが、その影響がこういう形で現場に及ぶというのは、想像以上に大きいと感じた。
この「教員不足」は、熊本だけの話でもない。全国的に、学校の先生が集まりにくくなっているというニュースを耳にする。たとえば近年、少子化の一方で働き方改革が叫ばれ、先生たちの仕事量を減らそうという動きはあるものの、教員に求められる役割はむしろ増えているように見える。行事や保護者対応、ICT活用など、やることは山積みだが、待遇がさほど良いわけでもない。結局、「割に合わない職業」となれば、教員志望の若者が減るのも無理はないのかもしれない。