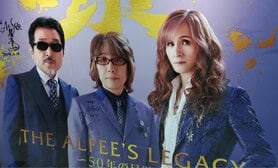無意識を可視化するタロットの世界
この時期にカガミに原稿依頼となると「新年の星占い」と相場が決まっているのだが、今回は「何でも書いていい」というありがたいご依頼(すでに星占いはたくさん書かせていただいているので、ぜひ各種女性誌とかWeb記事を見てくださいね)。
お言葉に甘えて星占いではなくタロットについて少しお話をしてみたい。タロットなんて……というなかれ。実はコロナ以降、世界的にタロットは大きな注目を集めている。英語圏でもZ世代からタロットは大きく支持されているし、手前味噌になるが、「ユリイカ」というちょっとハイブロウな文芸誌で2021年に僕が編んだ本格的タロット論集が異例のヒット、発売前重版。創元社からは全12巻のタロットアートブックを出してこちらも好評をいただいている。東京・浅草橋にはタロット輸入会社が「東京タロット美術館」を3年前にオープンさせて内外からの訪問者を集めている。海外に目を向けるとつい先日も、フィリピンで大規模なタロットイベントが開催され、600人以上の来場者があったそうだ。
タロットは単なる占いの道具にとどまらず、文化現象といえる注目の的になっているのである。
ただ、考えてみれば当然のことかもしれない。タロットの歴史は実にハイブリッドで多様、興味深いのである。タロットが誕生したのは15世紀半ばのイタリア。中国で発祥した紙のゲームがアラブ世界に入り、14世紀には西ヨーロッパに伝わる。ポロのスティック、金貨、杯、剣という4つのスートからなる原トランプを、イタリアのルネサンス貴族たちは最新の舶来の遊戯として楽しんだのである。その原トランプに、ゲームをより洗練させようと、切札を追加した天才……その正体はいまだ謎だ……がいた。タロットとしてすぐ思い浮かぶ「死神」「運命の輪」などの寓意画の札がプラスされたのだ。そう、タロットの誕生である。ここで選ばれたモチーフは、当時、よく知られていたさまざまな寓意画である。古典期の伝統を継承して、ルネサンスの人々は「時」「節制」「賢慮」「正義」「愛」「愚行」といったさまざまな抽象概念を寓意像として好んで描いた。公正さを示す天秤と峻厳さを表す剣を手にした「正義」の像は、今でも裁判所に見ることができるが、こうしたよく知られた寓意画がタロットの切札として採り入れられていったのである。一見謎めいたタロットの絵であるが、当時の文化を知っていればその意味を読み解くことはかなりの程度できる。逆にいえば、タロットの魅力的な絵を手掛かりに歴史を知ることもできる。タロットは「図像学」の恰好の題材でもあるのだ。最初は手描きの豪華なものだったタロットだが、すぐに木版画として大量生産されるようになり、イタリアからフランス、スイスなどを経て広くヨーロッパにタロットの遊戯は広がっていく。地域や時代によってさまざまなバリエーションがあって、これもコレクターの眼を楽しませている。ただし、ここで「遊戯」といっていることに注目されたい。タロットはもっぱらゲーム用であって、占いに用いられるような神秘性はなかったのである。