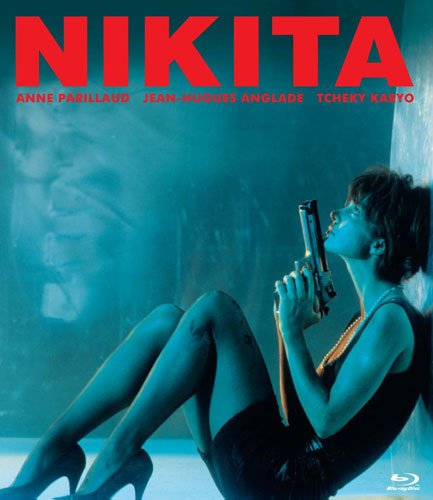
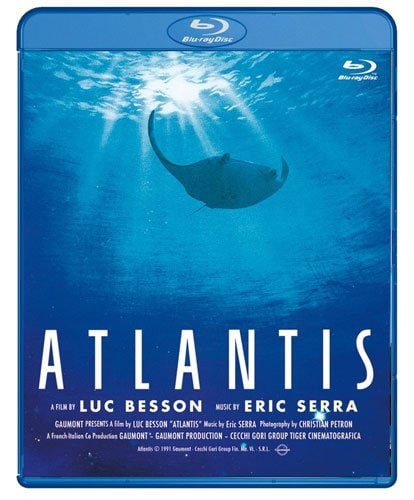

映画音楽というものが好きである。
ブルーレイとかDVDとかビデオなどというものがこの世に現れるまで、映画は映画館で観るものであり、あとは、テレビ放送を待つしかなかった。
そんな時代、映画好きな人々は、お気に入りの映画をもう一度観たいとか、その映画に関するものを持っていたいとか、まだ見ぬあこがれの映画が映画館に掛かるまでイメージを膨らませるために、映画のサウンド・トラック盤を聴いていたのだ。
サウンド・トラックといっても、いくつかの種類がある。ここでは、映画に使われた音楽が入っているレコードやCDのことだ。この中にも、映画の音声と同じものが使われているものと、音楽だけが入っているものとがあった。
たとえば、古い話になるが、1968年のフランコ・ゼフィレッリ監督の映画『ロミオとジュリエット』の音楽は、ニーノ・ロータが担当している。音楽が素晴らしいのでサウンド・トラックのレコードを購入したのだが、内容は、音楽よりも台詞の方が多いので、驚いたことがあった。つまり、レコードでロミオやジュリエットの台詞を聴くことにより、映画の場面を思い出すためのものだったと思われる。
映画音楽というのは、クラシックとかポピュラーとかいうのとは、またひと味違う音楽のような気がするのである。映画音楽といっても、その映画のために書き下ろされたものもあれば、既存のクラシックやヒット曲を使用しているものもある。
わたしが、これまでの愛聴盤から紹介すると、フランシス・フォード・コッポラがプロデュースし、ジョージ・ルーカスが監督をした73年の『アメリカン・グラフィティー』などは、その映画の時代背景、62年ころにヒットした既存のポップスを使用している。つまり、サウンド・トラックそのものが、フィフティーズと呼ばれる50年代のヒット曲集になっているのだ。このサントラによって、わたしはロックンロールやドゥー・ワップなどを知ったものだ。
それからもう1枚、愛聴盤を紹介するとしたら、スタンリー・キューブリック監督、62年の『時計じかけのオレンジ』だろうか。
キューブリックは、音楽に造詣も深く、既存の音楽を使うにも、ひとひねりしている感じがひとくせある感じだ。この映画では、ベートーベンの第九番交響曲が、物語の中でも重要な役割を担っているが、その演奏をウォルター・カーロス(今では性転換をしてウェンディ・カーロスと名乗っている)のシンセサイザーを用いた曲とオーケストラの演奏とを両方用いていて、独特の世界観を作り上げている。
わたしはこのアルバムで、エルガーの『威風堂々』、ロッシーニの『泥棒かささぎ』などという曲を知ったが、なにより影響が大きかったのは、ヘンリー・パーセル作曲の『メアリー女王の葬送音楽』だろう。ここでは、シンセサイザーの演奏が使われているが、原曲を聴きたくなってしまったのだ。ヘンリー・パーセルは、1660年前後の生まれといわれている英国の作曲家だ。バッハが1685年生まれというから、25年ほど前の作曲家ということになる。わたしはこの曲により、バッハ以前の音楽、古楽というものに惹かれていくのである。
シンセサイザーと古楽という、言ってみれば、最新の音と昔の音楽を教えられたわけである。
このように、映画に使われる音楽は、さまざまなジャンル、新しい音、古い音が使われているのだ。
そういえば、映画音楽の中で好きな作曲家というものをあげてみたい。みなさんが、これをきっかけに聴いてみようかなと思っていただけたら、うれしい。
一番は、ニーノ・ロータだろうか。『ゴッド・ファーザー』や『太陽がいっぱい』などが有名だが、映画監督のフェデリコ・フェリーにと組んだ作品の音楽も素晴らしい。幾人かをあげるなら、『男と女』『白い恋人たち』などのフランシス・レイ、『シェルブールの雨傘』『おもいでの夏』のミシェル・ルグラン。普段聴くことの少ない国の音楽も新鮮だ。たとえば、ギリシャの『日曜はだめよ』のマノス・ハジダキス、ソ連時代の映画監督タルコフスキーの『ストーカー』『惑星ソラリス』のエドゥアルド・アルテミエフなども、聴いてみてほしい。忘れてはいけないのは、ヘンリー・マンシーニだろうか。『ひまわり』『ティファニーで朝食を』『酒とバラの日々』など、ジャズの世界でもスタンダードになっている。あげだしたらキリがないくらい、素晴らしい作曲家がたくさんいる。
そして、それらの仲間入りをしている素晴らしい作曲者の1人が、エリック・セラである。代表映画はといえば、『グラン・ブルー』(1988)、『ニキータ』(90)、『レオン』(94)、『フィフス・エレメント』(97)など、監督のリュック・ベッソンの世界は、セラの音楽なしでは成立しないのではないかと思うほどの重要な役割を果たしている。
電子音を効果的に使い、アジアのリズムなども取り入れて、独特の世界観を作り上げている。『フィフス・エレメント』の中で、頭が巻き貝の肝みたいな形をした宇宙人のオペラ歌手が歌うガエターノ・ドニゼッティ作曲の歌劇『ランメルモールのルチア』から、ロックっぽいリズムに変わっていくところなど、笑いたくなるほど楽しい。
ベッソンとセラのコンビの映画で『アトランティス 』がある。これは海洋ドキュメンタリーであるが、海の映像とセラの曲が、最初から最後まで絡み合って進んでいく。セラの曲ももちろんだが、マンタが出てくるところで流れるマリア・カラスの歌声とマンタの泳ぎのコラボは素晴らしい。曲は、ベッリーニの歌劇《夢遊病の女》だ。この使い方などもセンスのよさを感じさせる。
今回のライヴでも、映画の曲を演奏するとのこと、また、その際には、リュック・ベッソン監督がセラのために特別に監修した映画の名シーン映像と、光を駆使した演出も予定されているという。
今回、この文章を書こうと思い立ち、『ニキータ』を観なおしたところ、あまりのおもしろさに、『レオン』『グラン・ブルー』と続けざまに観なおしてしまった。
そういえば、殺し屋になったニキータは最初の仕事の前にシャンパンを飲むのだが、その銘柄が、テタンジェ・コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン。う~ん、美味しそうだ、飲んでみたい。誰か一緒に飲みに行きませんか? [次回6/29(水)更新予定]
■公演情報はこちら
http://www.tempoprimo.co.jp/contents/ticket/ericserra.html


































