
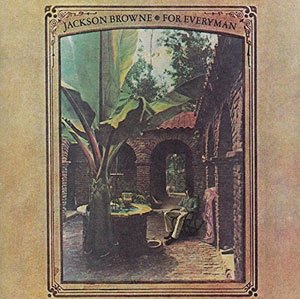
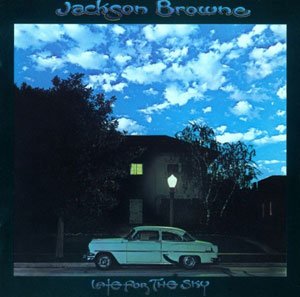
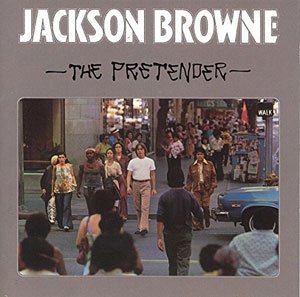
「仕事」といういい方は嫌いだが、ともかく、末席とはいえなんとか物書きの仕事をつづけるうち、どんどん引き込まれていった人たち(たとえば、エリック・クラプトン)や、あるいはまだなにもわからなかった段階でがつんとやられてしまった人たち(たとえば、ニール・ヤング)とは異なり、ジャクソン・ブラウンは、ちょうど大学に入ったころから、アルバム単位で、しかも同時進行で追いかけてきた人だ。いろいろな面で影響され、刺激を受け、その音楽を通じてさまざまなことを教えられてきた。
基本的には彼自身の実体験から生まれたものでありながら、聴く人それぞれがそこに自分自身の体験や暮らしを投影できる。あるいは、重ねられる。ジャクソンの音楽/歌は、そのように語られることが多い。僭越ながら僕も、20代を通じて、そういったスタンスで彼の音楽に接してきた。1977年春の、ローリング・ココナッツ・レヴューの一員として初来日以来、来日公演はほぼすべてを観ていると思う。
昨年(2015年)春の、新編成バンドとの来日時は、CSNのステージへの飛び入りを観たあと、名古屋の愛知県芸術劇場と東京のオーチャード・ホールを3回。いい歳をして、ほぼ追っかけ状態だ。最終日にはバックステージで少し話すこともでき、忘れられない思い出となった。
ジャクソン・ブラウンは、1948年10月9日、父親の赴任地だった旧西ドイツのハイデルベルクという都市で生まれている。アメリカに移ったのは、3歳のころ。少年時代は、ロサンゼルス/ハイランド・パーク地区にあった祖父の館で暮らしていたそうだ(セカンド・アルバム『フォー・エヴリマン』のジャケット写真はそこで撮られたもの)。
熱心なジャズ・ファンで、ドイツ滞在中にはジャンゴ・ラインハルトと演奏したこともあるという父に導かれ、ジャクソンは、早くから音楽に興味を持つようになった。ジョン・レノンと誕生日が同じだということもあり(8歳下)、当然、彼が15歳のときにアメリカ上陸を果たしたビートルズからはさまざまな影響を受けているはずだが、本気でミュージシャンになりたいと思うようになるまでの強烈な刺激を与えられたのは、ローリング・ストーンズだったという。具体的には、16歳になったばかりのころ、カリフォルニア州ロングビーチで観た彼らのコンサート。女性たちの投げるブラジャーやパンティーが宙を舞う光景を目にして、「これだ!」と思ったそうなのだ。のちに彼が書く歌たちのイメージとはかなりかけ離れた感じの、じつに意外なエピソードだ。
その後、本来の意味でのフォークに惹かれていったジャクソンは、短期間ながらニッティ・グリッティ・ダート・バンドで経験を積み、19歳のとき、ニューヨークのグリニッジヴィレッジに向かっている。ボブ・ディランの存在が頭のどこかにあったのだろう。この時期、彼はニコと親しくなり、彼女のアルバム『チェルシー・ガール』の制作にも協力。ここで「ディーズ・デイズ/青春の日々」がはじめて録音されている。
ニコと別れ、ロサンゼルスに戻ったのは1968年。そして、すでにこの連載で何度か触れてきた、ローレル・キャニオンやエコパークでの出会いや交流をへて、72年1月、最初のアルバム『ジャクソン・ブラウン』を発表。翌年秋には《青春の日々》や《テイク・イット・イージー》の彼自身のヴァージョンを収めた『フォー・エヴリマン』、74年秋にはマグリットを意識したものだというジャケット・アートも印象的な『レイト・フォー・ザ・スカイ』、76年秋には本連載1回目でも軽く触れた『ザ・プリテンダー』と、つぎつぎと上質な作品を生み出し、時代をリードするシンガー・ソングライターとしての地位を確立していった。 [次回4/27(水)更新予定]


































