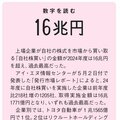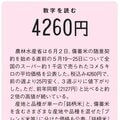物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。AERA 2024年8月12日-19日合併号より。
* * *
「君の能力を、社会のために使ってほしかった」
21年たった今も、そのシーンは鮮明に思い出せる。教授は穏やかな口調だったが、がっかりした顔をしていた。
情報工学を研究していた僕が選んだ仕事は、外資系証券の金利トレーダー。得意な数学を生かしたかったし、経済のメカニズムも知りたかった。学費を払いながら3畳一間で生活していた苦学生には、年収の高さも魅力的に映った。
それ以来、マネー資本主義にどっぷり浸かってきたが、社会的金融教育家として5年前から執筆や講演を始めたのは、恩師の言葉が引っかかっていたからかもしれない。
新NISAが始まり、お金の勉強をする人が増えている。上半期のビジネス書ベストセラー上位10冊には、僕の書いた『きみのお金は誰のため』をはじめ、お金の本が7冊も入っている(トーハン調べ)。
みんながお金を増やす方法を学べば、みんながお金持ちになれそうだ。しかし、それは実現不可能だ。金融市場で学んだのはまさにそれだ。
「社会全体のお金は増えない」
もちろん、自分のお金は増やせる。給料をもらったり、利息をもらったり、株の配当をもらったり。だけど、これらのお金はすべて誰かの財布から移動してきただけだ。給料は勤務先から、利息は銀行から、株の配当は企業から支払われる。全体のお金は一円たりとも増えていない。
「2024年3月末における家計の金融資産は過去最高の2199兆円を記録した」
先日のこのニュースにはカラクリがある。
よく耳にする金融資産という言葉。ここには大きな秘密が隠されている。金融資産のウラには全く同額の“金融負債”というものが存在しているのだ。金融とは、二人の間で行われるお金の融通のこと。早い話が貸し借りだ。貸す側には資産でも、借りる側には負債になる。