
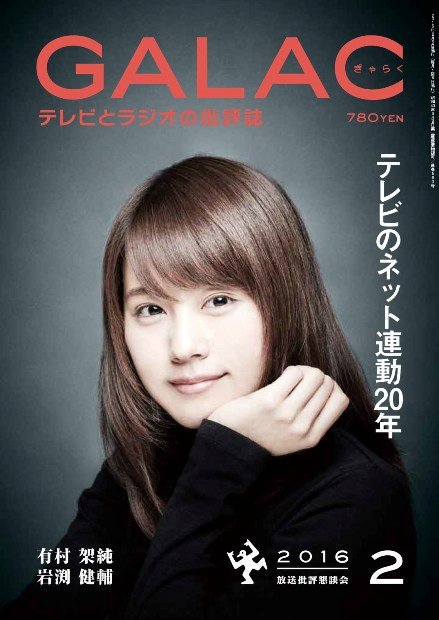
●AmazonでGALAC 2月号を買う

放送局は「放送と通信の融合」という課題にどう対処すればよいのだろうか。TBSテレビの柳内啓司氏が「制作」「宣伝」「流通」の3部門に整理し、論考する。
* * *
「放送と通信の融合」。この言葉を頻繁に聞くようになったのは2005年頃でしょうか。
それから10年。放送局はさまざまなパターンの「放送と通信の融合」に挑戦してきました。
例えば、ケータイから視聴者が参加できる番組を企画するといった「制作」面での融合。そして、番組宣伝のためにソーシャルメディアで活用するといった「宣伝」面での融合。さらには、放送した番組をネットで配信するといった「流通」面での融合。テレビのさまざまな面でネットを活用するケースは確実に増えてきており、私たちはそれを一括りに「放送と通信の融合」と言っているように思います。
そこで本稿では、このようにさまざまな使い方をされる「放送と通信の融合」という言葉を、「制作」「宣伝」「流通」3部門に整理し、それぞれの歴史について振り返ることで、テレビ業界の「これまで」と「これから」を考えていきたいと思います。
●「制作」における融合史 ――全ては「没入感」のために
まずは番組制作面におけるネット活用について考えていきたいと思います。
放送になくて、ネットにあるものは? そう問われた時に最初に挙がるものは「インタラクティブ性」でしょう。「放送と通信の融合」という言葉が叫びだされて以来、放送局各局は、ネットのよさ「インタラクティブ性」を活かした番組を多く制作してきました。ここではTBSで制作されたインタラクティブ番組を2つ紹介したいと思います。
一つ目は「大炎上テレビ」です。この番組は、MCが投げかけたテーマに関する意見を、視聴者がツイッター、または特別サイトから投稿でき、さらにそのコメントの一部は即時OAでダイナミックなCGスーパーと共に紹介される番組です。
例えば、「男は女を顔で選んでいる」といった賛否が分かれそうな問いに対して、視聴者は賛成か反対かを投票したり、意見をコメント。その結果をMCや番組出演者が取り上げ、さらに議論を深めていくといった具合です。これまでも、ファクスや手紙などで視聴者の意見を吸い上げる仕掛けを持った番組はありました。しかし、インターネットの登場によって、ほぼリアルタイムで視聴者の意見を吸い上げることが可能になり、ライブ感のある双方向性の強い番組を制作できるようになったわけです。
このようなリアルタイム・コミュニケーションができる番組を地上波で放送することは、技術的にはとても革新的なことでしたが、一つの悩ましい問題を抱えています。それはリアルタイムで大量に来るコメントを、なかなかさばききれないということです。





































