勤務先の病院の耳鼻咽喉科で組織検査を受けたところ、先に触れた「NK/T細胞リンパ腫」の診断が下りたのだ。治療ガイドラインどころか、この病気に対する標準治療もない時代。それでも師匠筋に当たる国立がんセンターの大津敦医師(現・国立がん研究センター東病院院長)に連絡すると、すぐに診察の手はずが整えられた。
2度のがんの経験は、診療姿勢も変えた
半ばあきらめていた宮田医師だったが、JCОG (日本臨床腫瘍研究グループ)の臨床試験が進んでいることを知り、参加を決意。4種類の抗がん剤と放射線治療の併用療法を受けたところ、「腫瘍消失」という“いい意味で想定外”の結果を得た。
「いまのような制吐剤もなく、放射線治療の副作用で味覚もなくなり、激しい口内炎もあって食欲は完全に停止。高カロリー輸液で栄養補給するだけなので、体重が10キロも落ちました」
ところがその苦痛は「あきらめ」を「希望」へと変えていく。
「こんなにつらい思いをして効かないわけがない――と(笑)」
予感は的中し、10週間に及ぶ治療を終えた1カ月後の検査で、腫瘍の消失が確認された。
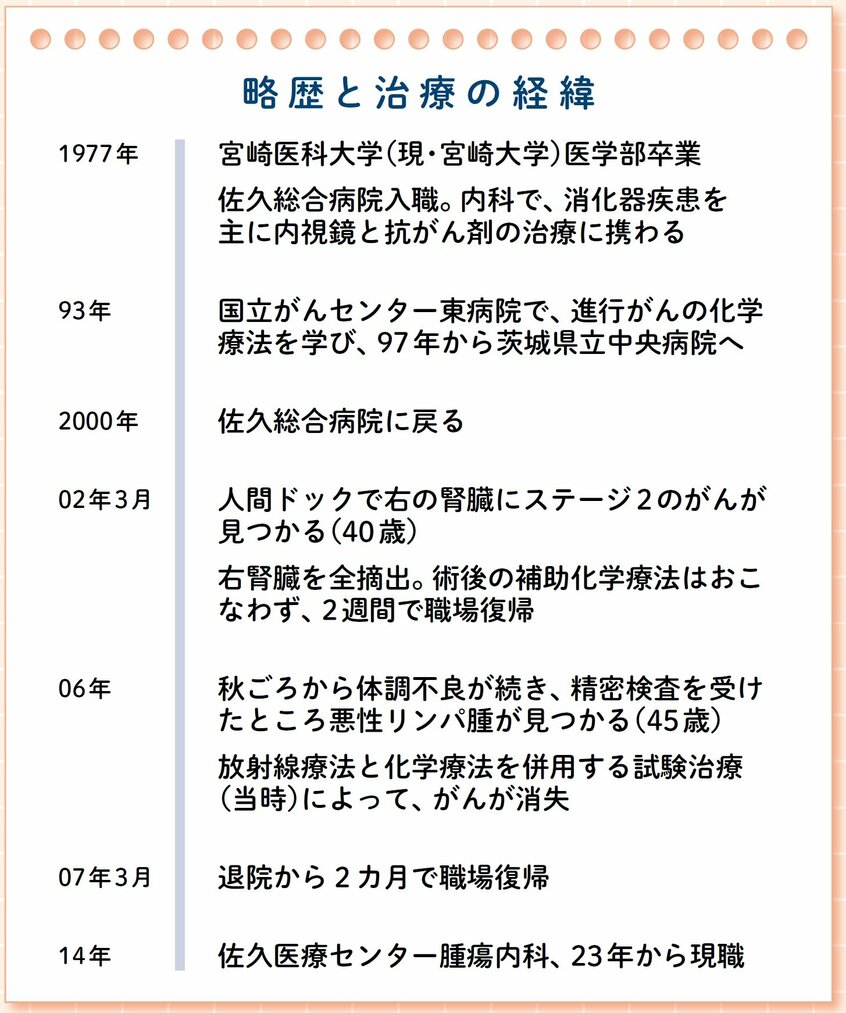
「医療界の人脈には本当に助けられたし、勤務先の病院でも多くのサポートを受けました。日々患者さんと話していると、職場の理解を得ることに苦慮するケースをよく耳にするだけに、そこはラッキーだと思います」
2度のがんの経験は、宮田医師の診療姿勢も変えた。
「患者さん自身が病気をどこまで消化しているのか――を考え、心理状態に合わせた話をするようになりました」
現代において、がんは「死」とイコールではない。しかし、絶対的な存在感を伴って「死」を意識させることは確かだ。
「自分ががんを経験したことで、死を身近に感じるようになりました。それまで死を意識することなどなかったけれど、いまは違う。いつ死が訪れても不思議ではない、と。平均寿命の80歳まで生きられたら御の字ですよ」
いまでも時々、腹筋が引きつれるような感覚や、鼻血、鼻水など、治療の後遺症と思われる症状が出ることがある。
「そんなちょっとした症状や、体調に変化が生じたときなどに、『がんの再発か?』とおびえることはあります。やっぱりどこかでこわがっているんですね」
そう苦笑する宮田医師の言葉には、がんを経験した者だからこそ発せられる温かみがある。





































