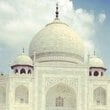ロシアがウクライナに侵攻してから1年半。いまだ終結への道筋が見えない。背景にあるロシアと米国の思惑、その責任は。長期化するウクライナ戦争について、東野篤子・筑波大学教授に聞いた。AERA 2023年8月14-21日合併号の記事を紹介する。
* * *
ウクライナ侵攻について、米国とロシアの責任を比べることはフェアではありません。いかなる理由があろうとも、侵攻を開始したロシアの責任が圧倒的に重いことは、疑いようのない事実です。
5月、ウクライナのゼレンスキー大統領は、G7広島サミットに参加するために緊急来日し、インドなどグローバル・サウスの首脳らと対面し、平和と終戦の条件である「平和の公式」を説明し、理解を求めました。サミット期間中には、米国のバイデン大統領が「戦闘機連合」への参加を表明し、希望する国が米国のF16戦闘機をウクライナに対して供与することに合意。さらに操縦士訓練の支援も明言しました。それらの成果を得たゼレンスキー大統領は6月以降、ロシアへの「反転攻勢」を開始しています。
ウクライナは「反転攻勢」を可能な限り早く開始したいと考えていましたが、欧米からの兵器支援が遅れ、なかなか開始する態勢が整いませんでした。開始後も、兵器や訓練の不足が裏目に出て、ウクライナ側に多大な犠牲を出しています。それでも少しずつ領土奪還は進んでいると主張していますが、この一連の流れから、ロシアはウクライナを完全に見くびっているのが現状です。
侵攻開始から1年半。中国やアフリカ諸国のように両国に停戦を呼びかける動きもありますが、ロシアはさらなる動員のための準備を整えつつあるとも指摘されます。ロシアには停戦の意思は全くなく、戦争を拡大する方向に動いているようです。プーチン大統領は、時間はロシアに味方すると考えているのでしょう。欧米諸国からの支援が先細り、ウクライナ全体の弱体化を期待していると思われます。
過小評価で長期化
一方、7月の北大西洋条約機構(NATO)の首脳会議では、ウクライナを複数年にわたって支援する方針を盛り込んだG7の首脳宣言が発表されました。これは戦闘が長期化してもNATO諸国は支援をやめないというロシアへのメッセージでもあります。とはいえ現状は、ロシアが軍事的優位を保っていることは確かで今後、ウクライナが反転攻勢を継続していくためには欧米からの追加支援が鍵です。