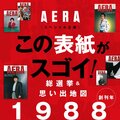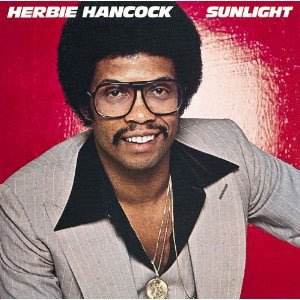
冒頭から個人的な昔話で恐縮ですが、少々お付き合いください。
ぼくが初めて海外取材に行ったのは、1979年、アメリカだった。西海岸で開かれていたモンタレー・ジャズ・フェスティヴァルの取材が主な目的だったが、ロサンゼルスを拠点にしていたため、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ジョー・ザヴィヌル、ミシェル・コロンビエの自宅取材も行なった。いまにして思えばずいぶんと豪華な顔ぶれだが、当時ミシェル・コロンビエは、ハンコックやジャコ・パストリアスやマイケル・ブレッカー等が参加した『ミシェル・コロンビエ』が輸入盤として出回っていた程度で、コロンビエは「なんで日本から取材にやってきたのか」と訝しげな表情を浮かべていた。
いちばん驚いたのが、ハービー・ハンコックの自宅を訪問したときだった。時期としては、ハンコックがヴォコーダーという最新秘密兵器を使って「ヴォーカリスト」としてデビューしたと話題を集めた『サンライト』や「ディスコに挑戦!」とこれまた騒がれた『フィーツ』が発売されたあと、さらにいえば『MR.ハンズ』の発売1年ほど前という、こうしてアルバム・タイトルを挙げるだけでなにやら騒々しくも楽天的な空気の漂いが感じられる、そのような「フュージョンな季節」の真っただ中だった。
さてハンコックのスタジオは、ガレージを改装した簡易的なものだった(じつはそれが簡易的なものではないということに、そのときのぼくは気づいていない)。各種キーボードが「これでもか」と並べられ、積み上げられ、そのキーボードの前に設置された小さな椅子以外に演奏するスペースはどこにもなかった。周囲にはワケのわからない器械や器材が巨大な壁をつくっている。それは少なくとも当時のぼくの「遅れた感覚」からすれば、スタジオではなく、何かの操縦席か実験室に映った。そこには「音楽」の匂いも気配も感じられなかった。しかしハンコックは熱心に説明をくり返し、「ここをこうするとこういう音が出るんだよ」と実践してくれる。ヴォコーダーを通して歌ってもくれた。それはまぎれもなく『サンライト』の音だった。ハンコックがきわめて優秀な技術者としての知識と見識をもち、録音(宅録)及び器械マニアであることを、あとになって知った。
フュージョンあるいはクロスオーヴァーと称される音楽は、ミュージシャンの個性や音楽性といった従来の前提条件に加えて、最新技術に対する知識と適応性そしてその「器械」を肉体化する「新しい発想」が求められた。しかもそれを体得し表現するまでに十分な時間を費やし、経験を培う物理的余裕を与えられることはなかった。それは一種の競争であり、生き残るよりも淘汰される確率のほうがはるかに高かった。そしてハービー・ハンコックは、その先頭に立ち、誰よりも速く走りつづけ、フュージョン時代が過去になった現在でも「現在進行形」としての強度と耐久性をもった音楽をつくった。加えて当時のハンコックの音楽には、職人としての凄みと殺気のようなものが感じられる。
『サンライト』は、前述したようにヴォコーダーの導入がひとつの注目点となったが、一方では曲ごとに入れ替わる共演ミュージシャンも話題を集めた。とくにジャコ・パストリアスやトニー・ウィリアムスの参加は、「この手の音楽に弱い層」からも支持された。そしてふり返れば、フュージョン時代のハンコックは(と限定すること自体、この多種多様多彩な天才には不適当なのだが)、作曲家そして全体のサウンドを組み立てるオーガナイザーとして(最初でもなく最後でもない)絶頂期にあったことに思い至る。なによりも楽曲としての完成度とハンコック自身の演奏が際立ち、その魅力と吸引力は、時代やジャンルを超えて、いまなお威力を発揮している。これはとんでもないことだと思う。懐かしいけれど新しい。『サンライト』で聴かれるような音楽は、日常のなかに無数にありそうで、しかしなかなかないと思う。[次回5/12(月)更新予定]