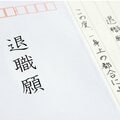「過去に評価済みのESを読み込ませ、ほぼ人間との評価にずれがない状態を保てています」
ソフトバンク(東京都港区)の担当者はそう話す。同社は17年からESの評価にIBMのAIシステム「ワトソン」を使う。AIが不合格と判断したESだけを人が見ることで、合否判断にかかる時間は75%削減されたという。
サッポロビール(東京都渋谷区)はAIを導入したことでESの読み込みにかかる時間が40%程度削減できた。
「その分、学生と社員が直接交流する時間を増やすことができると期待しています」(人事部)
今年からAIを使う住友生命(大阪府大阪市)も「AIがはじき出す評価やデータなども参考にしながら、多様な人材の取りこぼしを避け、求める人材の確保につなげたい」(人事部)という。
千葉商科大学専任講師(労働社会学)の常見陽平さん(44)は「AI導入は、学生にはチャンスだ」とみる。
「万単位の応募のある企業の一部では、これまで学歴などで線引きして選考を進めざるを得ない部分もあったが、AIの導入ですべてを見ることができる。大学名に関係なく、優秀な人材を掘り起こせるのではないかと期待を持つ企業もあります」
(編集部・澤田晃宏)
※AERA 2018年4月23日号