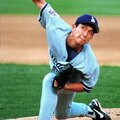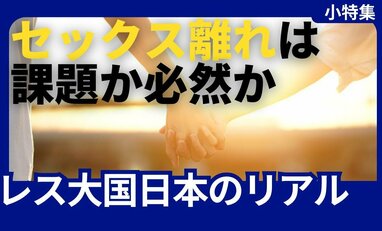エルカミーノ病院では指示に従い、食事や薬などを運ぶロボット「タグ」が活躍(撮影/ジャーナリスト・瀧口範子)

発展著しいロボット分野だが、アメリカではすでに医療現場での実用化が進んでいる。
深夜、入院患者の容体が変わったと米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)メディカルセンターから連絡が入った。脳外科医のポール・ヴェスパ氏は、自宅のコンピューターを立ち上げ、病室の場所を入力。「分身」を向かわせた。
「分身」とは「テレプレゼンス(遠隔存在感)・ロボット」と呼ばれる新しいロボットの一種「RP-VITA」。高さ152センチで、上部には大きめのタブレット大のスクリーンが付いている。RP-VITAは、ベッド脇に到着すると、スクリーンを患者に向ける。スクリーンにヴェスパ医師の顔が映し出され、患者は本人がそこにいるように感じることができる。
一方、ヴェスパ医師の自宅のパソコンには、RP-VITAのカメラがとらえた患者の様子、血圧や心拍数などのデータが映し出されている。適切な処置を看護師に伝えて診察が済む場合も多い。ヴェスパ医師は言う。
「これまでは20分で終わる処置のために、往復2時間かけて病院へ戻っていましたが、それがRP-VITAのおかげでなくなりました」
医師はゆっくり静養して翌日の勤務に備えることができる。テレプレゼンス・ロボットは、専門家が貴重な時間を有効利用するのを助ける道具として期待されている。
※AERA 2014年2月3日号より抜粋