

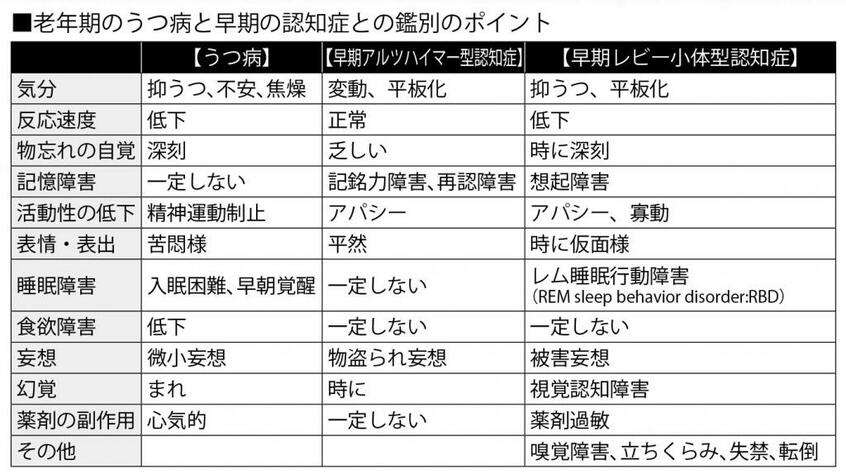
社会の高齢化に伴って増加している高齢者のうつ病。年齢のせいだと見過ごされたり、認知症と間違われたりして受診につながりにくいことも。自殺によって死に至ることもある病だけに、適切な治療を受けることが大切だ。
【かかりやすい年代、主な症状、治療法など…高齢者のうつに関するデータはこちら】
* * *
高齢者のうつ病は、高齢者人口の10~15%程度はいると考えられている身近な病気だ。老年期うつ病とも呼ばれ、ほかの年代のうつ病と区別されることがある。症状や治療法など基本的には共通しているが、高齢者特有の誘因や症状があり、それに伴って治療のアプローチが異なることもある。
高齢者のうつ病は高齢になって初めて発症した場合と、過去にうつ病になり、高齢になって再発した場合とに分けられる。うつ病はストレスなどによって脳の働きに問題が起きて発症するとされる。代表的な症状は「抑うつ気分」で、明らかな誘因や理由がなくても気分が落ち込み、空虚感や絶望感などが現れて、それが長期間持続する。
真面目で几帳面な性格の人ほどストレスをためやすく、うつになりやすいと言われている。しかし高齢になって初めて発症した場合、性格の影響は少ない。順天堂大学順天堂越谷病院メンタルクリニック教授の馬場元(はじめ)医師はこう話す。
「高齢者のうつに大きな影響を与えるのは、加齢による脳の変化です。動脈硬化などによって脳の血流が悪くなると血管障害を起こしやすくなり、それがうつの直接の原因になる可能性があります。実際に高齢で発症したうつ病の患者さんの脳を調べると、高い確率で隠れ脳梗塞が見つかるという報告もあります」
脳の変化に加えて高齢者特有の心理・社会的要因もある。高齢になると、次々と「喪失体験」を経験しやすい。親やきょうだい、配偶者、同世代の友人との死別、定年退職や子どもの独立など役割の喪失、さらに身体機能の喪失もある。目が見えにくい、耳が聞こえにくい、以前のようにからだが動かないなど身体機能の低下を感じたり、病気にかかりやすくなったりもする。



































