

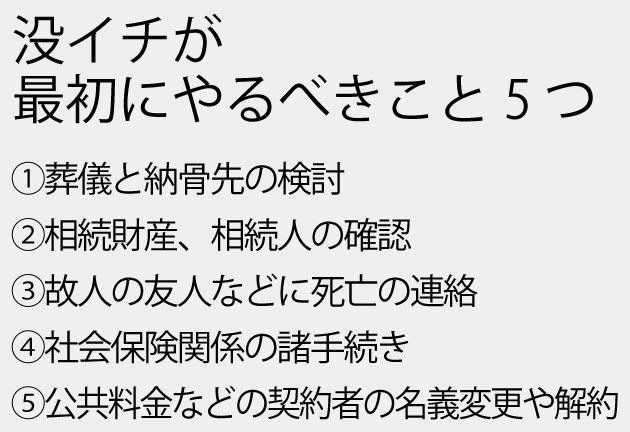

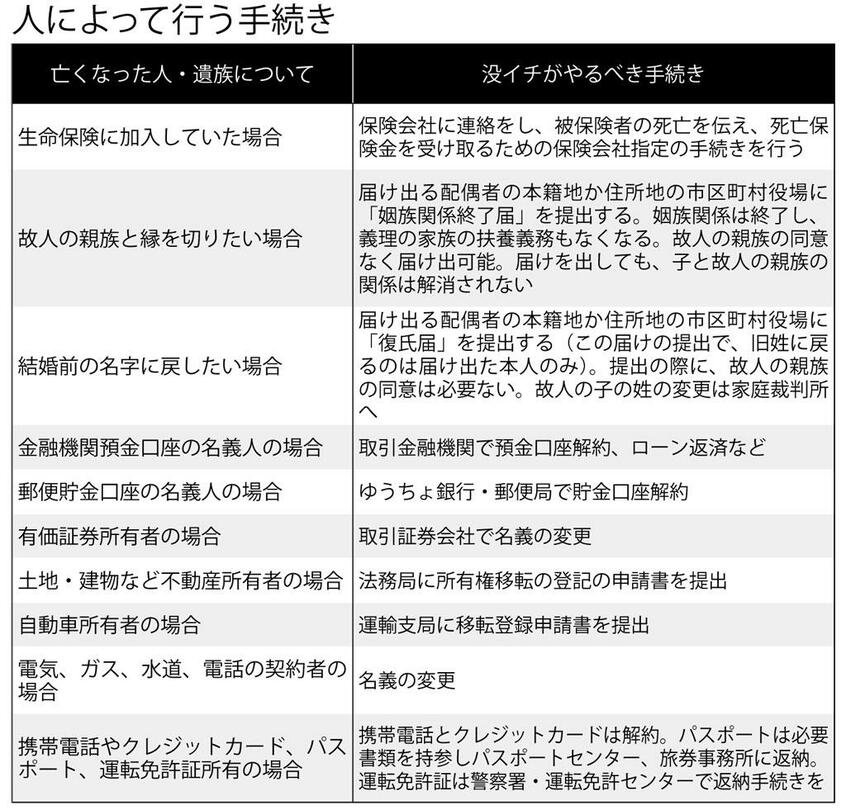
没イチという言葉をご存じだろうか。
配偶者が「没」し、一人になることで、「イチ」は1回を指し、2度目ならば「没2」。第一生命経済研究所主席研究員だった小谷みどりさん(現・シニア生活文化研究所所長・50歳)が広めた言葉で、離婚の「バツイチ」と異なるのは意思とは関係なく、避けられぬ「死」で一人になるという点だ。夫婦のどちらかが必ず没イチになる。
「死か没イチ、『DEAD or没イチ』なのです」(小谷さん)
小谷さん自身も夫を42歳で失っている。2011年4月、シンガポール出張の日の朝。起きてこない夫を不審に思い、寝室をのぞくと、夫の腕は布団からだらりと落ちていた。
あ、死んでいる!
夫の死を悲しむ余裕もなく、刑事組織犯罪対策課と書かれた名刺を持った刑事が自宅に入り、事情聴取を受けた後、警察署に向かい、結局、遺体は解剖に回された。内臓がすべてなくなってセミの抜け殻みたいになって戻ってきた夫が本当にかわいそうで、涙が出たという。
「私がボケたら介護してね」
「するする。おむつも替えるし、面倒みるよー」
1週間前に、そんなたわいのない会話をしたばかり。二人に子どもはおらず、共稼ぎ。
「身の丈に合った」都内のマンションを数年前にキャッシュで購入していた。いずれはマレーシアに移住しようね、という夢もあった。二人にいつか別れがやってくるとしても「死ぬのは私が先という前提でいつも考えていたんです」(小谷さん)。
しかし、夫は逝ってしまった。心不全だった。電球交換一つとっても、いつも夫がそばにいて、なんでもやってくれていた。これからは全てひとりで行わなければならない。人生の孤独感に襲われた。
「悲しんでも、もう夫は戻ってこない。同じ生きなくちゃいけないのなら、めそめそして暮らすより、亡くなった夫の分まで生きようと思う」
夫の分まで2倍人生を生きると決めた。
死を悲しんでいる暇はなく、翌週には、立教セカンドステージ大学の講義のため教壇に立った。小谷さんはここで「最後まで自分らしく」という講義を担当しているからだ。立教セカンドステージ大学とは、50歳以上のシニアを対象にした学びなおしの場。クラスには、小谷さんの1年前に「没イチ」になった庄司信明さん(59)もいた。ある日、小谷さんに、こう聞いてきた。
「ご主人を失ったばかりなのに、なぜ小谷先生はそんなに明るくいられるんですか」「ご主人の親御さんとはどうつきあっているのですか」
没イチならではの悩みは、没イチになってみないとわからない。改めてそう感じた小谷さんは15年、「没イチ会」を立ち上げた。現在、没イチ会には、5人の女性を含む12人がいる。
没イチになってもどうすれば幸せに生きられるのか? ヒントや陥りやすい「落とし穴」を考えてみる。





































