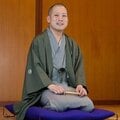なぜだろうかと考えてみたのだが、噺家は若いうちから同業者が亡くなるのを身近に見てるからじゃないだろうか。噺家は「定年のない職業」だ。定年=死。だから現役の先輩が亡くなるたびに、前座のころから通夜・葬儀の手伝いを年に何度もするのだ。仲間の死が身近だから、極端な話、「そのうちみんな死ぬ」という真理が知らず知らずに肌に染み込んでいる。だから不謹慎なコトを口にしても、あっけらかんとして笑いに繋がるのではないか。落語に人が死ぬ噺が多いのもその理由かもしれない。落語世界の住人の死も、リアルな噺家の死も極めて身近ですぐそこにある。
話を戻すと、知名度抜群の歌丸師匠に対し、若手がちょっと乱暴なコトを言えばお客さんは笑いやすい。安易といえば安易だけど、落語に不慣れなお客様を前に、私も恐縮ながら師匠をネタにさせて頂いたことがある。案の定ウケるのだが、反応の良さと裏腹になにかモヤモヤしたものが……。「歌丸師匠」の大きさばかりがのしかかり、己の無力さを痛感。「これじゃいかんなぁ……」と思いつつ、ついつい手が伸びる麻薬のような師匠の知名度。自分がネタにされる側にならなきゃならんのだが……いつのことやら。『世代交代』なんてくるのだろうか。だって歌丸師匠の師匠・桂米丸師匠が93歳で現役バリバリなのだから。なんか凄い世界に入ってしまったものだ。
※週刊朝日 2018年7月27日号