
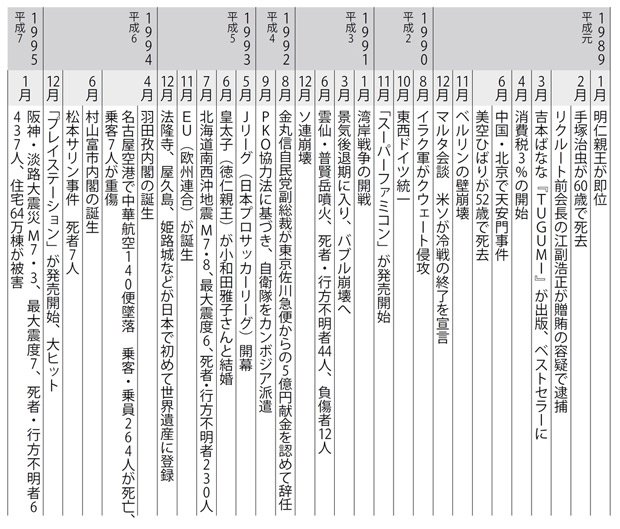
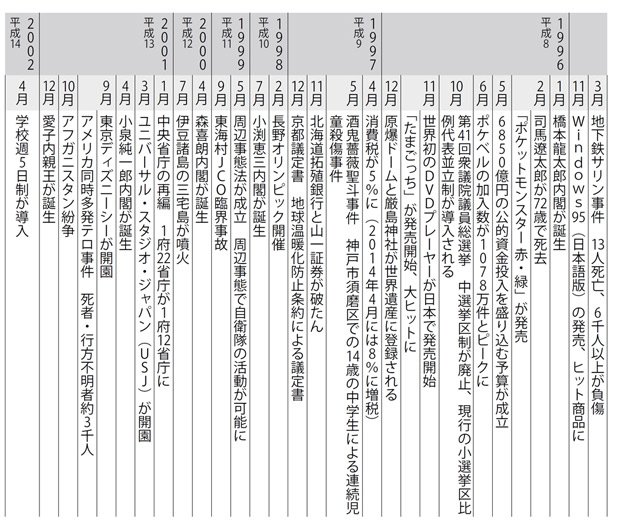
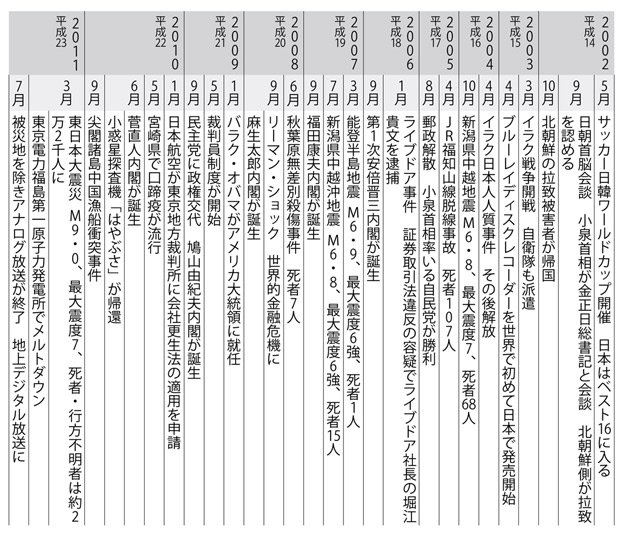

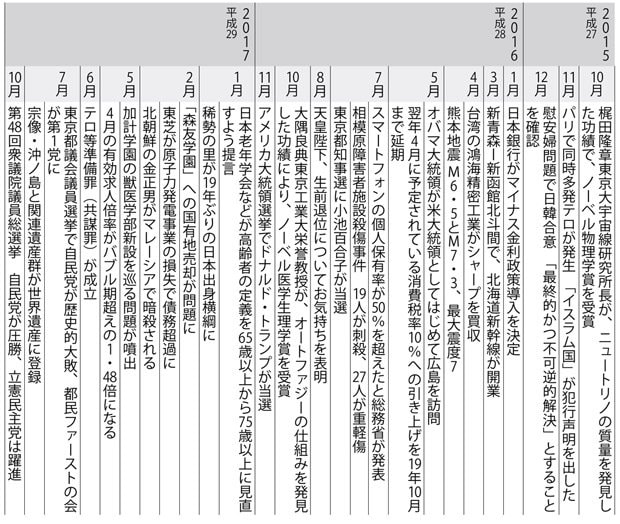
天皇陛下が2019(平成31)年4月末に退位する。私たちが生きてきた「平成」という時代は何だったのか。週刊朝日 新春合併号では、政治や経済、事件・事故や芸能、スポーツまで、その分野を代表する識者に「平成30年史」を語ってもらった。その中から、東大先端研究客員教授(政治学)・御厨貴氏が語った「平成の政治」を紹介する。
* * *
平成の政治は「改革」というキーワードを追ってきた。90年代に中選挙区制をやめて小選挙区制にした。自民党は派閥でお金を集めていたのが、政党助成金で賄われるようになった。公認権が重要になり、政党助成金の配分も総裁と幹事長が握るようになった。
大きな変化は政権交代が2回あった。ただそれが、みんなあまりハッピーじゃなく、政権交代に悪いイメージがついてしまった。細川政権や民主党政権は「統治」に慣れていなかった。自民党は痩せても枯れても50年統治の政党としてやっていて、手なれている。
民主党政権は官僚を敵に回し、子どもっぽい施策で国民に飽きられた。そこで安倍さんが日本国憲法が成立してから初めて、総理にカムバックした。これほど長期政権になるとは誰も思わなかったが、小選挙区と政党助成金の効果が「安倍一強」に表れている。
安倍さんは今回の衆院選でも改革を強調したが、そのキーワードは使い古されている。平成は政治的には「改革の30年」だったが、そろそろ終わる。次は「保守」という言葉が前面に出てくると思う。今回の衆院選で野党のうち希望の党が「改革保守」、立憲民主党が「リベラル保守」と、どちらも「保守」を掲げたことは印象的である。
今の若者の政治動向は極めて保守的だ。自民党支持の最大の理由は自民党政権しか知らないこと。昔の自民党政権は中に多様な派閥を抱え、外にイデオロギー色の強い野党・社会党があり、緊張感があった。今の若者は現にあるものを受け入れ、変えようという動機づけがない。就職も売り手市場で不満を持たない。
日本全体が「今のままでいい」となっている。安倍政権は国会やメディアでたたかれ支持率が下がっても、また上がる。昔なら内部抗争が生じ、やがて政権交代となったが、そんな混乱を望まない保守的な気分が横溢している。
一方で、時々反乱現象も起きる。小池さんは都議会で勝ったが、国政では数カ月で違う結果になった。国民の気分の変わり方は、「ジェットコースター」のようになっている。
今の安倍政権は、あたかも「永遠の今」のように見える。しかし現実には永遠はない。いずれは壊れる。政治は自分の時代だけじゃなく、その後をどうするかまで考えて初めて政治になる。昭和の政治はたらい回しと言われたが、自民党にそれぞれ派閥の長がいて、順番に政権を担ってきた。今はそんな派閥の長はいないし、次の人材も生み出していない。政権が終わりを告げたときどうするのか、今から考えておくべきだ。
天皇陛下の退位問題も、本来はこれまでの政権が早めに動いておくべきことだった。天皇陛下が自ら国民に向かっておっしゃるのは、異例のことだ。統治の主体である内閣を乗り越えて直接メッセージを発し、解決の糸口をつくった。崩御による交代の原則に例外を認めたことで、天皇陛下の地位は昔より不安定になる。平らかになるはずだった平成は、様々な不安定要因を抱えて終焉を迎えるのだろう。(構成/本誌・直木詩帆)
※週刊朝日 2018年1月5-12日合併号





































