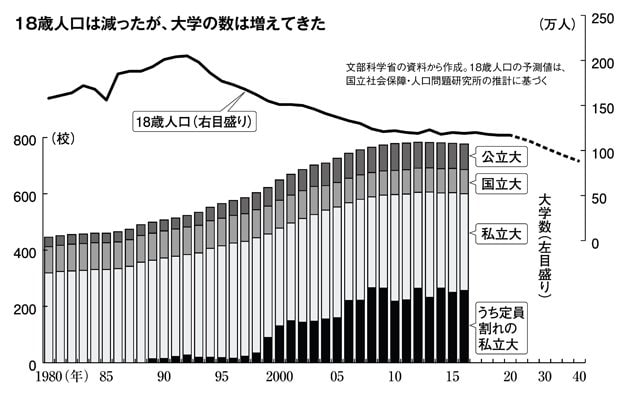
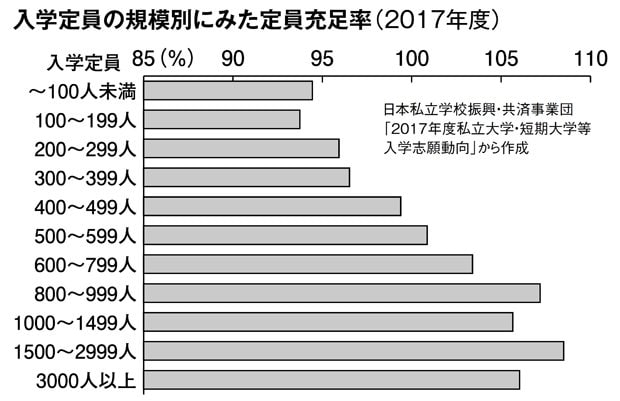
地方を中心に存続が危ぶまれる私立大学は多い。それを解決するためには「職員の力」が必要だと元桜美林大副学長の諸星裕氏はいう。
* * *
日本の大学の問題点は、立派な建学の精神があっても、どんな教育や人材育成をするかのミッション(使命)が明確でないことです。研究者の養成、勤労者の育成などと具体的に定めないと、カリキュラムに反映することもできません。
例えば、金沢工業大は教育の徹底を掲げ、学生の力を高めている。偏差値は高くないが、上場企業などへの就職に強い。教員と職員がミッションを共有して、一丸となって取り組んできた成果だと思います。
大学の改革には教員とともに職員の力が重要です。
かつて立命館大は入試担当の課長を予備校から招き、受験者を10万人規模に増やした。司法試験対策などのダブルスクールも学内につくった。職員は高校や予備校、企業と接点を持ち、学生の入り口も出口も知る存在です。職員ならではの発想で、改革できることも多い。日本の大学は職員の立場が弱く、見下すような教員さえいるのは残念です。
私は米国と日本でそれぞれ20年ほど、大学の教員や大学管理の仕事をしてきました。米国の大学も1980年代に危機を迎えましたが、その際に大学の外部開放を進めました。出前授業や週末授業を広げ、私の勤務先の大学は、4人に1人が25歳以上や既婚者の学生となるほどでした。





































