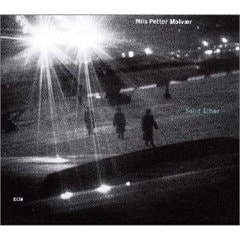
●“遅れてきた者の淋しさ”
私がジャズ雑誌で働くようになったのは1990年の春のことだったと思います。“と思います”というのは、なんとなく編集部に行ってバックナンバーをタダ読みしていた時期がけっこうあったからです。そして発送、梱包、校正、割付などの作業や取次店への挨拶等を覚え、どうにか形になりはじめたのが1992年頃からです。この2年の間にアート・ブレイキーやマイルス・デイヴィスが逝き、「マウント・フジ・ジャズ・フェスティバル」から“ウィズ・ブルーノート”というフレーズがとれ、「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」は終わってしまいました。
「あのフェスティバルは面白かったなー」とか、「誰それに会ったときは嬉しかったよ。もう死んじゃったけどね」といった諸先輩方の言葉をきくたび、私はよき時代への郷愁をかきたてられると共に、“遅れてきた者の淋しさ”をも感じました。そして「動けるうちはとにかく動き回る。聴きたいCDは万難を排して聴き、ライヴに接することができるのなら最大限にかけつける」ことを決意し、今に至っています。
●大規模なジャズ・フェスが復活
2000年代に入ってから間もない頃でしょうか、「東京で久しぶりに大規模なジャズ・フェスティバルが開かれる」という情報が飛び込んできました。私はわくわくしました。まだ誰が出演するかもわからないのに、その広い会場で音楽を楽しんでいる自分の姿が浮かんできました。
その後フェスティバル名は「東京JAZZ」、開催場所は東京スタジアム、音楽プロデューサーはハービー・ハンコック、という情報が入ってくるたびに、「今度こそ俺は間に合ったのだ」という、一種名状しがたい気持ちになりました。
フェスティバルは昼の1時頃から夜の9時過ぎまで続いたように思います。始まってからの数時間は太陽の光がガンガンに照り付けていたことを記憶しています。正直言って「暑すぎて音楽にまで気が廻らない。しかも音響も良くないし」という感じでしたね。といってもこれは約10年前のこと。当時の日本にはまだスコールもなかったはずですし、“熱帯雨林気候”でもありませんでした。
●キューッ、ピュー、プハーッ
日が沈もうというころ、白いシャツと(確か)ジーンズに身を包んだ男がステージに登場しました。トランペットを持っていなければ、誰がミュージシャンと思うでしょう、といいたくなるほど“そのへんのガイジンのアンチャン”感が漂っています。彼の名前はニルス・ペッター・モルヴェル。1980年代にはアリルド・アンデルセン(ベース)やヨン・クリステンセン(ドラムス)と共に“マスクアレロ”というバンドを組んでアコースティック・ジャズを演奏していましたが、2000年代に入ってからエレクトロニクスやターンテーブルを導入したグループを結成、その日本での初お披露目が「東京JAZZ」のステージだった、というわけです。
ニルスはトランペットを吹くだけではなく、吸ったり吐いたりしてもいました。キューッ、ピュー、プハーッといった音が、エフェクターを通したマイクを通じて観客に届きます。私は前もって彼の当時の最新作である『ソリッド・エーテル』や、その前の『クメール』を聴いていたのですが、「ああ、あの音はこうやって出しているのか」と初めて目で確認したという感じです。
もうひとり、私の関心を集めたのがギターのアイヴィン・オールセットです。空間を音の余韻で埋め尽くすようなプレイ、適度に粘りつつもエッジの立った音色に、私はテリエ・リピダルからの強い影響を感じました。もっとも後日取材したときには、「リピダルの名前は知ってるけれど、まったく影響は受けていない」と言っておりました。
第1回「東京JAZZ」でハービー・ハンコックが何を演奏したのかはまったく覚えていませんが、ニルス・ペッター・モルヴェルたちのパフォーマンスは今もしっかり、脳内で再生することができます。


































