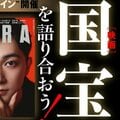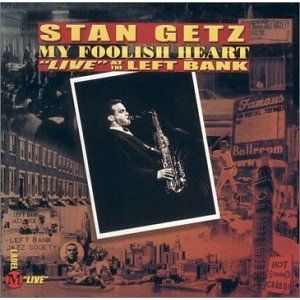
●ビ・バップは米の飯
「今も昔も大好き」(A)
「昔はすごく好きだったが、今はそれほどでもない」(B)
「昔は大して興味がなかったが、今は大好き」(C)
「昔も今も大して興味なし」(D)
どんな音楽ファンでも、以上4パターンにミュージシャンをわけることができると思います。
私の場合、(A)に相当するのがチャーリー・パーカーやバド・パウエルです。米の飯や、水と同じでいくら味わっても飽きない。その都度「おいしいなあ」と溜息をもらすのみです。
(B)に相当するのは、正直に申し上げればハービー・ハンコックやマッコイ・タイナーといったところでしょうか。音楽活動を長く続けるのは大変なんだなあ、と気の毒に感じてしまうこともしばしばです。
(C)に相当するのはスタン・ゲッツやJ.J.ジョンソンです。彼らのプレイがあまりにもスムーズで流暢過ぎるものだから、若き日の私は「軽い」「薄い」と誤解してしまったのですね。今聴くと、アドリブの密度の濃さ、難しいことを楽々と聴かせる表現力に脱帽です。
(D)は、そうだなあ…。20数年もこの世界にいると、ジャケット、曲目、楽器編成、メンバーを見れば、そのアルバムが自分の心に響くかあるいは不快な気分にさせられるか、わかるぐらいにはなりますね。
●初ゲッツに、「スカスカ吹いてんじゃねえよ」
私が初めてスタン・ゲッツの演奏を聴いたのはNHK-FMのラジオ番組で、でした。1970年代後半のことだったと思います。DJは本多俊夫さんでした。本多さんは白人のジャズが好きで、よくデイヴ・ブルーベック、アート・ペッパー、ビル・エヴァンス等をかけていました。
当時のDJで私の好みに合う選曲をしていたのは断然いソノてるヲさんでした。ラムゼイ・ルイス、ホレス・シルヴァー、カウント・ベイシー、アート・ブレイキー等、キャッチーでノリのいいものをガンガン紹介してくれたからです(オスカー・ピーターソンには、いささか食傷させられましたが)。
いっぽう本多さんの特集は、当時の私にはいささか退屈なものでした。スタン・ゲッツのプレイも、「なんだか高くてスカスカした音で、軽く流して気取って吹いている」ようにしか聴こえませんでした。それはボサ・ノヴァを演奏しているものを聴いたときも同様でした。
●遂にゲッツの良さが分かった!
が、突然、「フヌケ」にしか聴こえなかったゲッツの音が、私の心を揺り動かしました。そして「実は音色が分厚くて力強い」、「それぞれのフレーズに歌心があり、それらがつながることによって比類なきアドリブの世界が構築されている」、「リズム感も滅法よく、流暢ではあれどダラダラ演奏しているところは皆無」ということに、やっと気づきました。
きっかけは80年代後半、『ヴォエジ』というアルバムがFM番組で流れた時だったと思います。番組を途中から聴いたので、私はそれがゲッツの演奏であることがしばらくわかりませんでした。1、2曲かけ終わってから、DJのひと(誰だか忘れた)が、ゲッツの名をアナウンスしました。ああ、スタン・ゲッツってこんなに良かったのか。いままでオレは彼の何を聴いてきたんだろう。
うまくいうことはできませんが、目の前に“スタン・ゲッツ”という、まだ自分の分け入っていない巨大な密林が鮮やかに姿を現したのです。「わかりやすくて有名で、入門者でもすんなり楽しめる演奏家」といわれるゲッツの良さが、ジャズ・ファン歴10年にしてようやく体感できたのです。
以来、ゲッツは私のフェイヴァリット・ミュージシャンのひとりであり続けています。40年代のプレスティッジ録音に鳥肌を立て、その後のヴァーヴ録音にスリルを感じ、70年代の過小評価ぶりに怒り(『ザ・マスター』、『マイ・フーリッシュ・ハート』は最高傑作クラスだと思います)、亡くなるまで常に美しく鮮やかなプレイを繰り広げたゲッツに敬服するのみです。
初めてブルーノート東京にいったとき、店内にアンケート用紙があったのを記憶しています。「ブルーノートで聴きたいアーティストは?」という質問がありました。私はもちろん「スタン・ゲッツ」と書きました。その時、彼が末期がんに冒されていたとはつゆ知らず…。