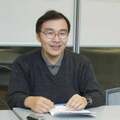「自分は社会的に許されない存在だ」と強く自覚したのは16歳のころ、初恋がきっかけでした。初恋の相手は同性。それは自分の性的指向に気づいただけに止まりません。同性愛者が自殺を図るリスクは異性愛者の男性よりも5.9倍も高いこと(「LGBTのいじめ、ハラスメント等による社会的費用推計研究会」調査より)や、地元の公園で同性愛者が狙い殺される事件を知ります。これらの事実は、将来、自分の身に「自殺」や「他殺」が起きてしまうのでは、と悲観させるものでした。
「社会的に許されない存在」だと思わされることは、本人の孤立につながります。喜久井さんも自身の性的指向は隠し、周囲の価値観に合わせようと、「自分を偽りながら周囲にウソを重ねて生きてきた」と言います。自分を偽ること、これがなによりも苦しかったそうです。
また、喜久井さんは16歳のころから現在までの15年間、両親と食事をしていませんでした。
10代のころ、喜久井さんは、自分を「家庭内に住み着いた乞食」だと感じていたからです。働きもせず、学校へも行かず、それでもお金のかかった食べ物を口にすること、それ自体に罪の意識を毎回、感じていました。しかも、その「醜態」を家族に晒すことは屈辱的であり、その視線から逃げるために食事を自室に運んでいました。
両親は過干渉気味で、いつも喜久井さんを幼児に接するように扱うため、それもまた苦しかったそうです。
喜久井さんは毎食、用意された食事を盗むように素早く手に取り、自室にこもる。あるとき、お箸をとり忘れてしまったことがあり、素手で食事をしたこともあったそうです。
両親に会うのは一日一度でも苦痛。箸を取り忘れたからと言っても、再度、顔を合わせる気にはなれません。そこでご飯は指を使い、味噌汁は舌を伸ばして舐めとって食べました。エサ皿に頭を入れる犬のような自分に「これが自分にふさわしい」と安堵感さえ感じたのだと言います。
もちろんその安堵感は偽物で、激しい自己否定感の裏返しだと言えるでしょう。