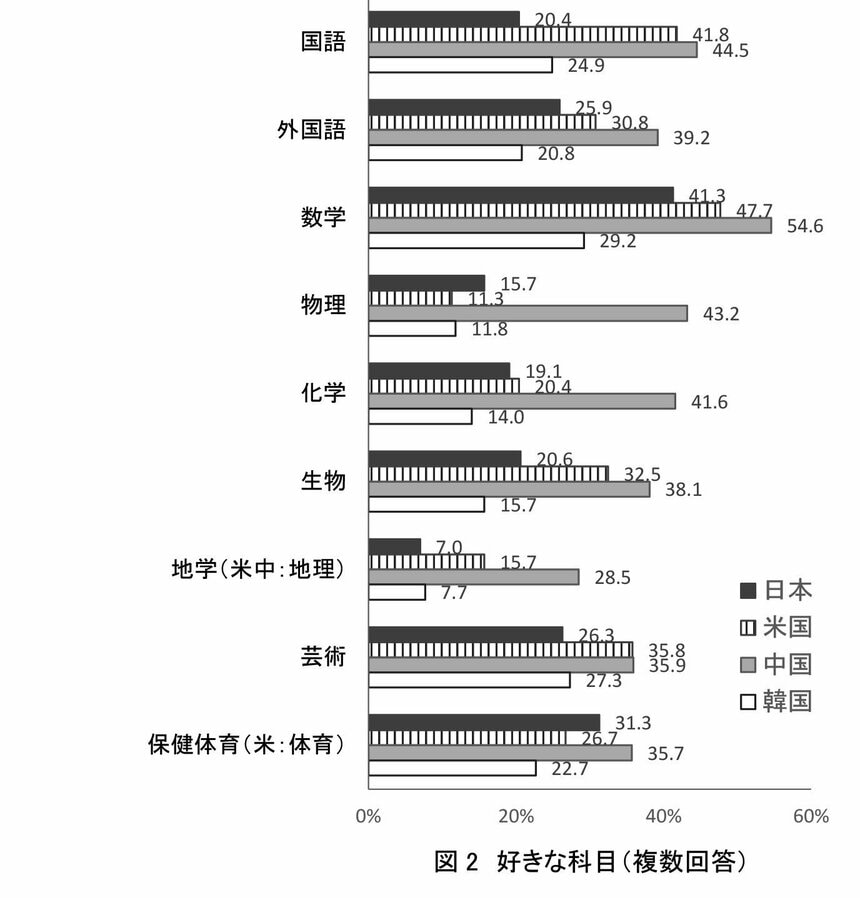年度の最後、生徒の感想は「この世の中は、何もかも法則にもとづいているということに気づかされた。ただ記憶するのではなく、自分たちで考え、話し合っていくことによって、その仕組みを本当に“わかる”ことができたような気がします」というものでした。実験がおもしろい、というのとも異なる視点です。「なんで物理や科学を勉強しなきゃいけないか」と先生が言わなくても、生きることと密接に関わっていると知ることができたのではと思います。
博士課程を出ても、“優位”に働かない?
――二つ目の理由、日本では「科学者や(理系の)研究者になっても社会的評価・待遇が低い」というのはどういうことでしょう?
SETAM教育や理系人材の育成などと言われてはいるものの、大学の研究費は十分とは言えず、世界では中国やアメリカが研究費を伸ばす一方、日本はほぼ横ばいで大きな差が生まれているといわれています。
また、欧米では、博士課程出身者は給料が高いことが一般的ですが、日本では博士課程を出たことが、そこまで優位には働かず、大学の研究職についても、研究者を減らしている大学も多い。研究者になっても未来が描けないなら、子どもたちは夢を持てないですよね。これは日本社会の問題だと感じます。米中韓に比べ理系の政治家が少ないのも背景にあるのかもしれません。
実際に、理科は役立つのか? 親のかかわり方とは
――実際に、理科は社会に出たときに役立つのでしょうか。
理科は失敗してもかまわない数少ない科目です。トライアンドエラーから本質を見抜く、これからの時代に不可欠な能力を身につけるのに最適です。この能力は、理系だけでなくどんな職業でも、普段の生活でも重要です。
――親は子どもに対し、どのように関わればいいでしょう。
家から駅への道、学童や習いごとへの道などで、子どもが不思議なことを見つけてきたら、「どうしてだろうね?」「不思議だね」「面白いことを見つけたね」と声をかけてあげる。親は教える必要はなく、興味を支えるのが仕事です。
次のページへ考える力を身につける方法とは?