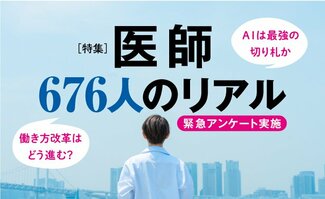プーチン氏は、ウクライナ全体が「ネオナチ」であるならば国の存在自体、認める必要がないと考えるに至ったのだろう。それが「ウクライナ」を演説で避ける原因ではないだろうか。
それを裏付けるようなプーチン氏の言葉がある。それは、4月27日に国会議員らを前に行った演説だ。ソ連崩壊に伴うウクライナ独立について「今後も友好的な国だという前提で受け入れた」と主張し、「歴史的なロシアの領土に『反ロ』が創設されることなど誰も予期しなかったし、そんなことは我々は容認できない」と述べたのだ。
一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの戦勝記念日の前日に公表したビデオ演説で、ロシア軍がナチスの残虐行為を再現していると非難した。
ゼレンスキー氏が着るTシャツの胸には、プーチン氏の心を見透かすかのように「私はウクライナ人だ」と書かれていた。プーチン氏がこれを見たとすれば、極めて挑発的だと受け止めただろう。
■米国一極支配への抵抗
プーチン氏が口にするのをはばかるほど忌み嫌う「反ロ的なウクライナ」。ここでの「反ロ」は、NATOへの加盟などの軍事的な意味合いだけを指す言葉ではない。
5月9日の演説では、ソ連崩壊後に「自分は特別だ」と考える米国に多くの国が服従したと指摘した上で、こう主張した。
「我々は異なる。ロシアには異なる性質がある。我々が祖国愛や信仰、伝統的な価値観、先祖代々の習慣、全ての民族と文化への敬意を捨てることは決してない」
米国による価値観の押しつけに屈することを道徳的な退廃と位置づけ、それに抗する崇高な戦いの中に、ウクライナへの侵攻を位置づけたのだ。
プーチン氏はここで「全ての民族への敬意」を強調している。これは、ウクライナの尊厳を踏みにじる今回の戦争と矛盾しないのだろうか。
実は、プーチン氏の頭の中では、話はまったく逆なのだ。ウクライナはロシアと一体不可分の民族だ。ロシアから離れようとするウクライナ人こそが、米国に魂を売った裏切り者だ。これが、プーチン氏の理屈だ。
こうして、プーチン氏の中では、ウクライナでの戦争は、米国の一極支配への抵抗という、より大きな戦いの一つの局面として理解されている。
最近は「ソ連崩壊後の一極支配の世界が崩れようとしている。これこそが重要なのだ。ドンバスやウクライナで起きている悲劇が重要なのではない」とまで言い切った(4月12日の記者会見)。
米国の価値観が及ばないロシア中心の世界を築く。ウクライナはそのために不可欠な領域だ。そう考えるプーチン氏の戦いは、まだまだ続きそうだ。(朝日新聞論説委員・駒木明義)
※AERA 2022年5月23日号より抜粋
 駒木明義
駒木明義