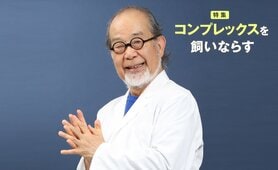研究ジャンルの中では人気の高い恐竜などの古生物研究だが、研究費削減の波は避けられないという。AERA 2019年10月14日号から。
* * *
恐竜のフィギュアを手に登場してもらったのは、古生物の研究者として知られる東京学芸大学准教授の佐藤たまきさん(47)。
51年前、東北の高校生だった鈴木クンが骨を発見したことからその名が付いた首長竜「フタバスズキリュウ」。2006年、この首長竜が、新種であるとする論文を発表し、世界から注目された。
マイナージャンルのなかでは、一般からの人気が高い恐竜などの古生物研究だが、ここにも研究費削減の波は押し寄せている。テクノロジーの進化が、かえって研究の足かせになることも。
「大きいのは文献ですよね。昔は図書館が学術誌を個別に購読していたのに、現在は少数の大手の出版社が販売する電子ジャーナルの高額なパッケージを購入しなければならない。いつでもどこでも手に入るのはメリットですが、資金面でのデメリットは小さくないです」
研究費が減額されているだけでなく、世界に対する競争力も落ちていることを感じる。
「学術全般を見ていると、これまでトップレベルだった日本が他国に抜かれて、昔はよかったという、さみしい雰囲気に。研究者は憧れの職業だったのに、今はリスクが大きすぎて、志望者も減っています。この先残っていくのは、好きなことをやっている人だけ。もちろん研究したいという人には教育を授けていきたいですね」
大学教員は、「零細企業の社長」のようなもの。学生の研究のサポートをしながら、自身の研究も進め、「仕事をしていない時間を探すのがむずかしい」日々を送っている。
とはいえ、好きなことをやっていい時間をもらったら「絶対研究をする」(佐藤さん)というほど研究が好き。その情熱に、未来の研究者が感謝する日は、きっと遠くない。(ライター・福光恵)
※AERA 2019年10月14日号より抜粋