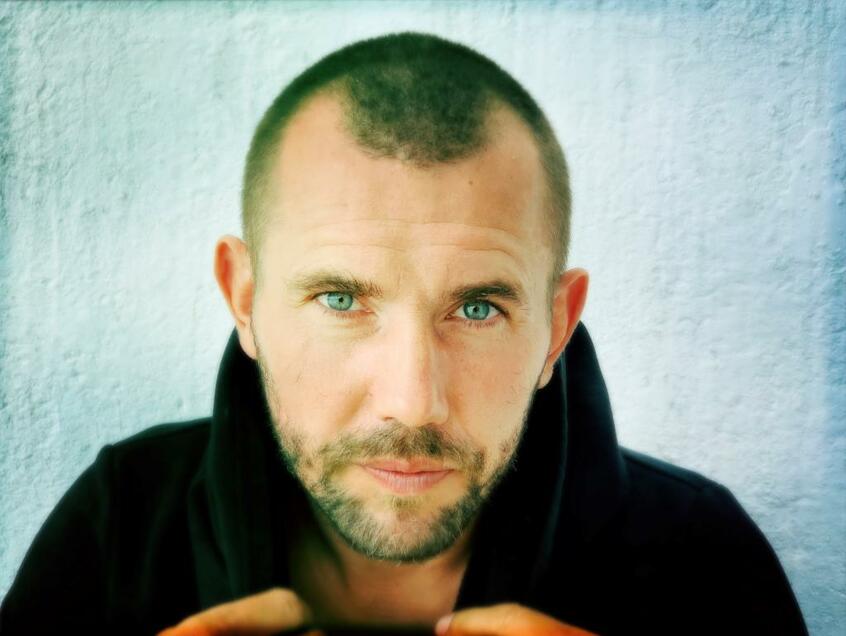
マンタスは特に、周縁化されたコミュニティー、絶滅の危機にあるコミュニティーに関心がありました。ウクライナはそもそもヨーロッパの端です。マリウポリには、「ギリシャコミュニティー」というかなり古いコミュニティーがあります。マンタスは戦争下におけるコミュニティーに興味があって、そこが関心どころだったと思います。彼の第1作「Barzakh」はチェチェンで10年から11年に撮った作品ですが、ここでも周縁に追いやられてしまった人々が、戦禍でどのように暮らしを営んでいるかを描いており、共通点があります。
――クヴェダラヴィチウス監督は取材開始から数日後の3月30日、現地の親ロシア派勢力に拘束され、殺害された。
4月1日に彼の第1作のラインプロデューサーから「マンタスが撃たれた」と連絡がありました。ハンナさんがフィルムと遺体をリトアニアに連れ帰りました。そして、私は彼の過去2作で編集を務めたドゥニア・シチョフさんと葬儀に参列。彼女に映像を見てもらったんです。「これで映画を作れると思います」ということでしたので、(映画のスタイルを)彼女の判断に委ねることに何の迷いもありませんでした。過去2作で監督と作業を行っているので、彼女は監督のビジョンを十分理解しています。資金も何も全くない状態でしたが、映画製作は監督のレガシーを伝える、監督の喪に服す作業になりました。監督の死に大変なショックを受けましたが、同時に、少なくともこの映画は監督が生きた証しになるという希望を込めました。
――5月のカンヌ国際映画祭に出品するため、製作は急ピッチで進められた。音楽や解説は一切なく、砲撃を受けた街、破壊を免れた教会の地下で助け合いながら生きる人々の姿を淡々と映し出す。
まずドゥニアさん、監督の恋人だったハンナさんがパリに2週間滞在し一緒に編集作業をしました。音響を担当した3人は24時間シフトを組んで、休みなく5日間で仕上げました。実はカンヌ国際映画祭の出品締め切りを過ぎていたのですが、選考チームに見てもらえるという約束を取り付けていたので、それに向けて製作しました。
字幕の予算は全くなかったのですが、(請け負ってくれた)会社が「予算は心配しなくていい」と、すぐ取りかかってくれました。それは本当に心が温まる経験でした。



































