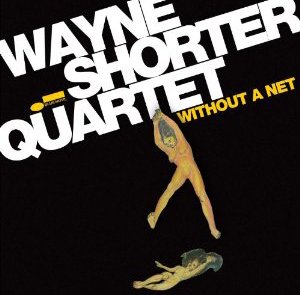

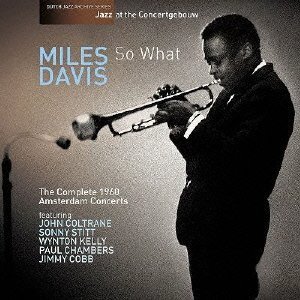

きょうも『ウイズアウト・ア・ネット』を聴いた。ウエイン・ショーターの新作。いいなあ。すばらしいなあ。ショーターの音楽は、遠回しの表現が多く、そのぶん面倒な面もあるが、ずいぶんと話が早くなった。若干の疑問点もないわけではないけれど、それはいずれ考えるとして、当分はこの圧倒的な音楽に身を預けよう。
ちなみにぼくは、楽しくスリリングではあるが重厚な音楽でもあるので、きのうは1曲目から5曲目まで、きょうは6曲目から最後の9曲目までといったふうに、2回に分けて聴いている(前後が逆の場合もあり)。
これって、きょうはA面、あしたはB面と、自分のペースで楽しみながら、ゆっくりと吸収しつつ音楽と接していたLPレコードの時代に近い。というか、ほとんど変わっていない。そしてぼくには、実(じつ)のある音楽と付き合うには、こういう聴き方がいちばん合っているように思える。A面もB面もないCDは単なる記録媒体にすぎないが、ああ、レコードとはなんと偉大な発明品だったのだろう。
ウエイン・ショーターと今回の新作については、4月6日に書店に並んだ『群像』5月号に短文を書いたので、お時間のある方はぜひ読んでください。タイトルは「ジャズを救う人」。そしてまだ聴いていない人は、一刻も早く聴いてほしいと思う。じっくりと腰を落ち着けて音楽を聴くという習慣が失われつつある現代にあって、この種の「すばらしい音楽」の居場所があるのかどうか、はなはだ疑問ではあるのだけれど。
世の中が「正しいこと」と「まちがっていること」だけでできていたら、どんなに楽なのだろうと思うが、幸か不幸かこの世の中は、「正しいがまちがっていること」と「まちがっているが正しいこと」によって成り立ち、その両者のせめぎ合いから日常というものが生まれ、ぼくたちはそのなかに飲み込まれ、日々翻弄されている。
しばしば目にする、「英語では、正しくはブルースではなくブルーズと発音します」という忠告は、ぼくには「正しいがまちがっていること」の象徴のように映る。そもそも「ブルースではなくブルーズと発音します」と書いている文章自体が日本語であるわけで、その意味では、すでにこの「正論」はツッコミ一発によって崩壊したも同然だが、この種の表記や発音に関する正誤に過度に神経を使う必要はないと思う。
音楽評論家という職業上、ミュージシャンやグループの表記にはそれなりに配慮はしている。「グラハム(Graham)」を「グレアム」と書き改めることくらいはしたほうがいいだろうと思い、そうする場合もないわけではない。「V」のカタカナ表記にも、それなりに気を配っている。気分としては「ベンチャーズ」だが、したがって「ヴェンチャーズ」と書くことが多い。そして「発音のまちがいは正し、より原音に近い表記に改めよう」とする意見にも同意できないわけではない。
しかし、とここで立ち止まる。多くの場合、そうした意見は、英語に関して指摘されることが多い。アメリカとイギリスのミュージシャン名にほぼ限定されているといってもいいだろう。そして、だからこそ軽症ですんでいると考える(なかにはすでに重症になった例もあるが)。
では、この症状が進行すれば、いったいどのような状況が待ち受けているのか。それこそ正論からすれば、正しい発音に基づいた表記は、英語のみならず、すべての言語に対して等しく扱われなければならない。それは、まさしく「正しいこと」だろう。その結果、どういうことになるかといえば、たとえば音楽関係の書籍や雑誌には、誰だかわからないミュージシャンやグループの名前が頻出し、まったく意味の通じない文章で埋められることになる。
一例を挙げれば、「ワルター・ワンダレー(Walter Wanderley)」は「ヴァルテル・ヴァンデルレイ」と書かなければならない。この正しい(とされる)発音に基づく表記で統一された誌面や文章を想像してみよう(くり返すが、そうして書かれた「正しい表記」は、しかし日本語で書かれているのです)。さらに加えて、世のお父さんたちは、当然のことながら、「レディオでナイト・ゲームを聞きながらビアでも飲むか」といわなければならない。
多くの音楽の原点とされる「ブルース(blues)」についても、「ブルースではなくブルーズ」という声が飛び交い、最近では「ブルーズ」と表記されている文章も増えてきたように思う。しかし前述したことと重なるが、ことは「ブルース」を「ブルーズ」にしただけではすまず、なかには新(正)表記と旧(誤)表記が混在したものも少なくない(たとえば、正しいとされる「ブルーズ」と、まちがっているとされる「アーロン・ネヴィル」の併記とか)。この「ブルーズ」と同じような例として、「マイルス(Miles)ではなくマイルズが正しい」とする声もある。
ぼくはこうした指摘や正論を、前述した「正しいがまちがっていること」の代表に挙げたい。そして結論めいたことをいえば、たとえそれが原音に忠実な発音や表記であったとしても、意味が通じない、あるいは通じにくいもの、言語的ストレスを感じさせるものであっては、それこそ「正した意味」がなく、そうであるとするなら旧来の表記のママでいいと思っている。
さらに加えて、表記が変わるということは、その表記にともなう時代性や個人的な思い出が消える可能性があることを意味し、それはどう考えても淋しい。たとえば「ピーター・ポール・アンド・マリー」という名称とともに青春時代を送ったオジサン・オバサンにとって、「ピーター・ポール・アンド・メアリー」は別人でしかない。ぼくはジョニ・ミッチェルが好きだが、「ジョウニ・ミチュル」という表記に出くわすと、やっぱり別人に思えて、その文章が遠いものになってしまう。
曲のタイトルに邦題があるように、人名にも邦題(日本語表記)があるというふうに考えているわけではないが、最も重要なことは、「馴染み」ではないかと考えている。それは年配の世代に限らず、若い世代にも共通している。つまり日本人として言語的ストレスや無意識の違和感を抱かせないような発音や表記というものがあり、そこに異を唱えることは、正しいかもしれないがまちがってもいる。たとえば日本では「ズ」を「ス」と発音することが多いが、それは「まちがったこと」なのではなく、日本人が選択した言語文化のひとつ(それは必ずしも世界に誇れるものではないかもしれないが)なのだろう。
以下は、植草甚一著『ぼくは散歩と雑学がすき』(70年、晶文社刊)の抜粋。この文章は1968年に書かれた。
「とうとう間違った発音のしかたでサイケデリックという言葉が流行するようになったな。こないだも新聞社の人が来たとき、サイキデリックと発音するのが正しいんです、といったけれど、そうですか、と返事しただけで話題を変えられてしまった。まあ、しかたがないや。ジェミナイという重要なオブジェクトを、ジェミニと発音したまま、とうとう訂正しないでいるジャーナリズムなんだ。アメリカ人がジャン・コクトーのことをカクトーと発音すると、つい相手の顔を見ないではいられなくなるが、サイケデリックと発音する人がいると、いつもこれと同じような気持ちになる。(中略)この辞典(ランダム・ハウスの英語辞典)は新語の収録が多いので評判になったが、25ドルだから1万円だし、ほしかったけれど、おいそれとは買えない。それを思いきって買ったのは、Psychedelicという言葉が出ている辞典は、いまのところ、これ一冊しかないと、なにかで読んだことがあったからである。(中略)じつはヒヤヒヤしながらPsychedelicを引っぱったところサイキデリックという発音記号になっていた。アクセントの位置はdelの綴りにあるが、説明が6行ついているので追記しておこう」
植草説が正しいかどうかはさておき、「サイキデリック」ではなく「サイケデリック」という表記を選択させたものが、いわゆる日本人の言語感覚だと思う。そしてこの言葉は、のちに「サイケ」と短縮されて使用されるようになった。「エレキ」とほぼ同じ運命を辿ったことになる。それにしても「エレクトリック・ギター」を、どこにもない「キ」をもってきて「エレキ」とした感性は、こっそりと世界に誇ってもいいのではないか。これもまた、「エレギ」と濁音でしめくくることにストレスを感じる日本人独特の無意識のアレンジなのだろう。
もうひとつの結論をいえば、少なくともぼくが会ったことのあるアメリカ人やイギリス人(ともに圧倒的にミュージシャンや音楽関係者が多い)には、「ブルース」と発音する人もいれば「ブルーズ」と発音する人もいた。その中間のような人もいた。あまり正確なことはいえないが、統計的には「ブルース」が多かったように思う。
同様に「マイルズ」に関していえば、「マイルス」が大半を占めている。たまたま最近、『コンプリート・アムステルダム・コンサート1960』というライヴ盤が発売されたが、改めて聴いてみると、冒頭で司会者のノーマン・グランツが「マイルス・デイヴィス」と紹介している。そういえば先に挙げたウエイン・ショーターの新作に関して、ドン・ウォズがブルーノート・レコードの公式サイトでインタヴューに応えている映像があるが、これも「マイルス」と発音している(ショーターの新作の1曲目は、マイルス時代の《オービッツ》の再演。同曲はマイルスの『マイルス・スマイルズ』に収録されている。よってドン・ウォズは「マイルス」を連発することに)。
マイルス関連でついでにいえば、『ビッチェズ・ブリュー』を『ビッチズ・ブルー』と正そうとする声があるが、これも身も蓋もない話ながら、『ビッチェズ・ブリュー』と発音するアメリカ人もいる。ヨーロッパのどこかでインタヴューに応えたマイルス自身が、たしか『ビッチェズ・ブリュー』と発音していた(ユーチューブを探せば出てくるはず)。ちなみにあるアメリカ人に聞いたところ、「ブルー」の場合は綴りが「blue」であり、それは「青」を指す、したがって「ブリュー」が正解に近く、しかしながら発音は「ブルー」と「ブリュー」の中間くらいかなという答えが返ってきた。
そうそう、マイルスと『ビッチェズ・ブリュー』といえば、もう一人の主役はジョン・マクラフリン(John McLaughlin)だが、本人に確かめた人から聞いた話では「マクローリン」という発音が正解に近いらしい。デビューした当時は「マクローリン」と表記され、その後「マクラグリン」を経て「マクラフリン」に落ち着いたが、なんのことはない、最初の「まちがっている」と非難された「マクローリン」がいちばん正しかったことになる。これまた余談だが、ウイントン・マルサリス(Wynton Marsalis)の場合、少なくともぼくは、「マーサリス」と発音するアメリカ人に会ったことがない。
『ボサノヴァの真実』(ウィリー・ヲゥーパー著:彩流社)という本が出版された。巻頭に近いページに「ポルトガル語の日本語表記について」として、何人かの人名が挙げられている。そして正確な表記を挙げた上で、「日本で定着していると思われる表記に準じた」と記されている。たとえば「アストルーヂ・ジルベルト」は「アストラッド・ジルベルト」、「ラウリンド・アルメイダ」は「ローリンド・アルメイダ」、「トキーニョ」は「トッキーニョ」といった具合。
前者が正しく、後者がまちがいというわけだが、著者が「まちがっているが正しいこと」を選択したことによって、よりわかりやすく、より読みやすくなっている(「ヴァルテル・ヴァンデルレイ」と「ワルター・ワンダレー」も挙げられている)。もしも著者が果敢にも、「《イパネマの娘》のヒットで有名なアストルーヂ・ジルベルト」という表記を選択していたら、じつにわかりにくく、読みづらいものになっていただろう(おそらく読者から「校正ミス」として指摘される)。
ぼくがさっきからいっていることは、つまりはこういうことなのです。それがいかに「正しいこと」であっても、すんなりと日本人の身体に入ってこないことには意味がない。なぜなら日本人を対象にした、日本語で書かれた文章なのだから。そこに「過度に正しいこと」が入り込める余地はないのです。さらにいえば、これは音楽に関わることだけではなく、ニッポンの英語教育そのものの問題であり、一時的かつ表層的な改訂は、結局は混乱を招くだけのように思う。
今回はここまでです。『ボサノヴァの真実』に関しては、次回で紹介したいと思います。はたしてぼくが探していた答えは書かれているのだろうか。なおこの原稿、ウエイン・ショーターの『ウイズアウト・ア・ネット』を聴きながら書いた、とすればエンディングとしては美しいが、とてもそのようなナメた態度でナナメから聴けるような音楽ではありません。あとは自分の耳で確かめてください。[次回4/22(月)更新予定]
 中山康樹
中山康樹

![群像 2013年 05月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/516L5kUrfPL._SL500_.jpg)














