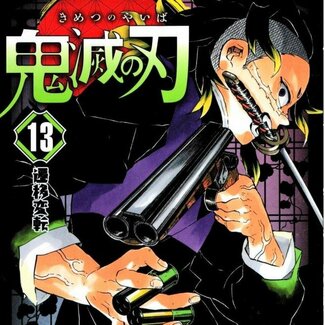その毒舌芸には、これまで数々の先人たちが引き継いできた歴史があるという。1960年代以降では、上から目線の高慢な態度で「バカヤロー」とたびたび毒を吐いた大橋巨泉が有名だ。80年代には、過激な毒舌漫才で絶大な支持を集めたビートたけしも象徴的な存在だろう。最近では、毒を含んだ「あだ名芸」で再ブレークした有吉や、ケンカを止めに入った人に対して痛い一言を突き付けて笑いをとるお笑いコンビ「鬼越トマホーク」も毒舌の“新興勢力”として台頭してきている。
彼らは先輩や権威ある立場の人などにも構わず毒を吐く。強い者に歯向かうことは危険な行為であり、だからこそ、そこに面白さが生まれるのだろう。
「毒舌芸はもともとは権力や権威、強いものを風刺して、庶民の不満を笑いに変えるものだったと思います。いわば庶民の“ガス抜き”だったわけです」(談四楼さん)
これは落語にも通じる部分がある。例えば落語の演目「目黒のさんま」だ。
ある殿様が立ち寄った目黒で、焼いたさんまを食べる。普段は食すことのないさんまに魅了され、殿様は後日、食卓にさんまを出すよう家来に命じる。家来たちは「脂が身体に障る」と考え、さんまを蒸して脂を抜いた。さらに、「小骨が喉に刺さってはまずい」と考え、骨を全部取りだす。殿様は「まずい」と驚き、仕入れ先を聞くと、家来は「日本橋魚河岸」と答える。これに殿様が、「さんまは目黒に限る」と言った、という噺だ。
無造作にさんまを焼けば美味だが、丁寧に調理したことでかえって味が悪くなったという滑稽さを描いている。締めの「さんまは目黒に限る」というのは、海のない目黒で捕った魚が美味だと断言する殿様が“いかに無知か”を揶揄したものだ。
「落語は直接的な毒舌は吐きませんが、権力者が滑稽な姿で描かれている。つまり遠回しに権力をからかって笑いものにしているのです」(談四楼さん)
今も昔も、人々のガス抜きの役割を担ってきた毒舌芸だが、そこには「毒を吐かれた相手すら救われる」という芸の境地がある。談四楼さんは続ける。
 井上啓太
井上啓太