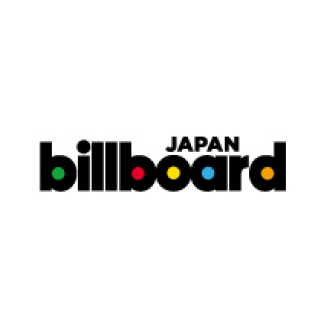川口成彦の“ピアニーノ”と、天羽明惠(ソプラノ歌手)が共演した【歌に恋するピアニーノ】と銘打たれた公演が、フランス発のクラシック音楽フェス【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】にて開催され、その公演レポートが到着した。
“ボヤージュ 旅から生まれた音楽(ものがたり)”というテーマ設定に、出演者たちがそれぞれユニークな回答ともいうべきプログラムで臨んだ2019年の【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】。このフランスで誕生したクラシック音楽フェス、朝早くから夜もかなり遅い時間まで公演が続く。その遅いほうの時間帯での開催がこのうえなく奏功した公演があった。
それが昨年ポーランドのショパン国際コンクール歴史的楽器部門で2位に輝いた川口成彦が、ドイツを中心に活躍するソプラノ歌手の天羽明惠と19世紀製のピアニーノ(アップライトピアノ)で共演した【歌に恋するピアニーノ】と銘打たれた、この公演だ。
ピアノという楽器は、19世紀のヨーロッパ都市部で爆発的な普及をみせた。産業革命が進むにつれ都市部に人口が集中、ピアノの需要も増えていった。やがて大人数を収容できるコンサートホールが続々登場、その大空間にあわせてピアノも世紀初頭の木製部分が多いモデルから、しだいに大音量が得られる金属フレームの楽器へと姿を変えてゆく。言い換えるなら、そうなる以前やそうなってゆく過程で存在した“歴史的ピアノ”の数々には、音量の拡大や安定感にこだわった現代のピアノとは違う、独特の魅力がそなわっている。
それを“現代ピアノへの発展段階”と考えるなら、音量の頼りなさや音色のばらつきに不足や不安をおぼえるかもしれない。が、実はそうした点こそがむしろ古い時代のピアノの美点だった。音域や鍵ごとに音色の傾向が違ったからこそ、全ての鍵から良くも悪くも均質な音が出る現代ピアノでは出せない、19世紀の作曲家たちが“ありき”で想定していた本来の音の陰翳に近づける。
現代ピアノに慣れた現代の聴き手がそれを再認識できるようにするためには、弾き手がそうした歴史的楽器をよく知るプロでなくてはならないのはもちろん、他にも工夫も必要だ。たとえば、それらの歴史的ピアノが本来的に存在していた“場”は今とどう違っていたか考え、当時の演奏環境に立ち返ってみること。当時のピアノが置かれていた空間の広さは、天井の高さはどのくらいだったのか。聴き手は何人くらいで、客席は楽器に対してどう並んでいたのか。あるいは、会場の明るさは……。
【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】2019年の【歌に恋するピアニーノ】という公演はその意味において、20:30開始という遅い時間帯を割り振られた時点で、すでに勝利が約束されていたと言ってよいかもしれない。
歴史的ピアノ、なかんずくアップライトの楽器ピアニーノは概して、家庭の居間などに置かれていた。仕事が終わり夕食を済ませた宵どき、19世紀の人々はそうしたピアニーノを囲んで、同じ楽譜をみながらピアノ曲を弾いたり、誰かがピアノの伴奏で歌ったりした。プロ音楽家たちを有力者が招いて行われたサロン音楽会などもその例にもれず、“音楽の夕べSoiree musicale”の名のもと、夕暮れ時に賓客たちを招いていた。演目はピアノ曲だけであることはまれで、たいていは歌い手やピアノ以外の楽器を弾く人間が加わり、ピアノ曲、歌曲、室内楽曲……と多様な曲種が披露された。そう言った音楽を、演奏者は壇上から聴かせるのではなく、客席と同じ高さの席で披露した。
川口と天羽のために用意された会場は、どちらかといえば広めの会議室に近いホールG409。これが理想的なまでに19世紀ヨーロッパのサロン空間といってよい空間だった。天井は高すぎず、妙に残響があるわけでもない。廊下を通って建物の一室にたどりつく……というアプローチもよい。ロマン派の作曲家たちのピアノ曲や歌曲が披露された場そのままだ。しかも、壁面に設置された燭台風の照明で、光量をそれなりに落としての演奏となった。集中力が高まる薄暗さ、19世紀の蝋燭照明もそのような感じだったのではあるまいか、
ピアニーノは壁面に向けて置く楽器ではあるけれど、会場では川口が客席を向く配置になり、めったに見られないピアニーノの裏面を眺めながらの演奏になった。音響を試行錯誤したうえでの判断とのことで、この点だけは歴史的観点から逸れたとも言えるが、結果的にピアニーノの細やかな音色の違いは最後列で聴いていた筆者にもよく感じ取れた。さらに言うなら、19世紀オリジナルの貴重なピアニーノの裏面など、めったに見られる機会があるものではない。貴重な機会を提供してもらえたと好意的にとらえたい。
演目はシューベルト(オーストリア)の「ハンガリー風メロディ」、メンデルスゾーン(ドイツ)の「ヴェネツィアの舟歌」、グリーグ(ノルウェー)の「四つのデンマーク語の歌」、モーツァルト(オーストリア)がパリ時代に書いたフランス語歌曲二つ、そしてショパン(ポーランド)の歌曲のフランス語版……と、随所に「旅」を意識させるものとなっていた。スマートフォンはおろかテレビもラジオもない19世紀、人々の空想力は今よりずっと強かっただろうから、こうした音楽の夕べに異国を想う音楽を楽しみ、つかの間の旅を疑似体験したに違いない。そんなことを思うプログラムだ。
ピアニーノは1840年製、製作元はパリのプレイエル。ショパンが愛した楽器の作り手だ。こうした歴史的楽器を何十種類もさまざま弾き親しんできた川口成彦は、鍵ごとにタッチの変化で大きく変わりやすい音色の違いを随時、試し愉しむように味わい深く聴かせてくれる。冒頭で演奏されたシューベルトの曲は川口自身も思い入れの深い作品とのことで、冒頭から楽器の性質をはっきり打ち出しつつ、ほんのり異国情緒漂う楽想をしなやかに“場”になじませていった。
日本では馴染み深いとはいいがたいデンマーク語の響きが旋律美に独特の風采を添える。心のなかの“旅”の気配。グリーグはノルウェーの作曲家だが、20世紀初頭に独立するまでノルウェーは長くデンマーク支配下にあり(19世紀以降はスウェーデン領)、現代のノルウェー語はまだ確立されていなかった。ともあれ、歌手自身がいうには「実はかぎりなくノルウェー風なデンマーク語」だったという。北欧語に覚えのある聴き手までも旅情をかきたてられる歌だった……ということか。
メンデルスゾーンの「ヴェネツィアの舟歌」では、時折聴こえる弱音のニュアンスが美しかった。ロマン派時代のドイツ人たちが南国へ寄せた思いは、太陽と歌だけではなかったのだろうと感じる瞬間であり、ピアノという楽器はそもそも“弱音(ピアノ)”を出せるのが強みだったのだ……と改めて認識させられる。
モーツァルトでは、19世紀のフランス人たちがこの数十年前の作曲家の曲をどんな音環境で聴いたか?の再現例になったかたちだが、天羽の声と溶けあいつつも随所で存在感をあらわす歴史的楽器の音色美が印象的だった。そして最後に、ショパンのピアノ曲を原曲にした歌曲「そり」「美しい日々」「水上の娘」。編曲者はイタリアの作曲家ボルデーゼ(1815~1886)だが歌詞はフランス語、そのあとアンコールで歌われたショパン歌曲にもとづくフランス語の「子守唄」とともに、詩句の流れに沿った天羽の細やかな歌い口が会場の薄暗さによくなじみ、絶妙の“音楽の夕べ”の締めくくりになった。
共演者同士が折々相手の出方しだいで音を重ねてゆく、その場の音楽的対話で紡がれてゆく演奏は両者の経験値と実験精神あればこそ。曲間で何度か演目について演者二人が説明を添え、客席とのあいだに寛いだ対話的空気が生まれていたのも筆者には好ましく感じられた。
終演し演奏者が去った後も、珍しいピアニーノをよく見ようと多くの人が楽器を囲み去りがたく留まっていた(筆者の視点からは、やや短く見える鍵盤と、譜面台の両脇にやや広く確保された正方形の燭台スペースが印象的に残った)。そうした近しい距離感で聴いてこそ、19世紀のピアノ音楽や歌曲は書き手がイメージしていた作品像に近づける……歴史的楽器による歌曲の夕べ、あの薄暗さや空気感など今後の音楽鑑賞のヒントも見せてもらえた公演だった。TEXT:白沢達生
◎公演情報
【“歌に恋するピアニーノ ”プレイエル製ピアニーノによる公演】
2019年5月5日 (日・祝) 20:30 ~ 21:15
東京国際フォーラム ホールG409:ラ・ペルーズ
◎曲目
シューベルト:ハンガリー風のメロディー D817 ロ短調
メンデルスゾーン:無言歌集第1巻から ヴェネツィアの舟歌 op.19-6
メンデルスゾーン:無言歌集第2巻から ヴェネツィアの舟歌 op.30-6
グリーグ:4つのデンマーク語の歌 op.5
モーツァルト:鳥よ、年ごとに K.307
モーツァルト:寂しい森の中で K.308
ショパン:24の前奏曲 op.28 から 第15番「雨だれ」
ショパン/ボルデーゼ:そり(マズルカ op.59-1歌曲版)
ショパン/ボルデーゼ:美しき日々(マズルカ op.59-3歌曲版)
ショパン/ボルデーゼ:水上の娘(バラード第2番 op.38歌曲版)