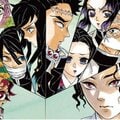マンネリ化するおうちごはんに簡単に変化をつけられる、香味常備菜。「和」「中華」「韓国風」など組み合わせは無限大。食欲が出る組み合わせのポイントなどを、AERA 2021年6月21日号から。
【料理研究家さわけんさん直伝! 香味常備菜「黄金レシピ」はこちら(全6品)】
* * *
科学する料理研究家のさわけんさんによれば、香味常備菜の作り方にはコツがあるという。
「ベースと、香りとうま味をうまく組み合わせることです」
さわけんさんによると、ベースになるものは水分や油分。ごま油やオリーブ油、醤油、ラー油などだ。
香りの素になるのは、いわゆる薬味になる香味野菜。ねぎや生姜、にんにく、ニラ、大葉などがあげられる。
うま味の素になるのは、だしの素や干しエビ、かつお節など。
ここに、七味や柚子胡椒などアクセントを組み合わせれば、大人ごのみの味わいになる。
「ベースには、オクラやメカブ、えのきなど『粘り』が出る食材を使うのもおすすめです。素材との絡みがよくなります。また、ベースとうま味が合わさったキムチの素やポン酢醤油、トムヤムペーストや味噌も使い勝手がよいです」
好みに応じて組み合わせは無限大。自分好みの香味常備菜を作る楽しみもある。風味も材料でがらりと変わる。
「『和』にするか『中華』にするか『韓国風』にするか。どの路線でいくかを考えても面白いと思います。干しエビやナムプラー、トムヤムペーストを使えばアジアン、トマト、ニンニク、オリーブオイルならイタリアン、チリパウダーを使えばアメリカンやメキシカンになりますよ」
■栄養面でもメリット
ただし、注意すべきは、「辛み」の使い方だという。ネギやニンニクは大量に入れても「辛み」がさほど強くならないが、生姜は入れすぎると口の中がビリビリしてしまい、万能ダレとして使いづらくなる。調整しながら加えていこう。同様に、醤油などの「塩味」も、最初に入れすぎると取り返しがつかなくなるので、少しずつ加えたい。
わさびや七味など、子どもが苦手な食材がある場合は、はじめからたれに混ぜずに、食べる時にそれぞれが加えるというのがおすすめだ。