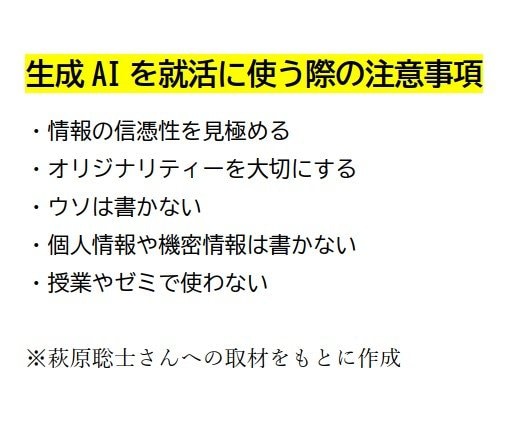
AIを使いこなすには
文章作成や長文の要約も、生成AIの得意ジャンルだ。使いこなすには様々なコツがあると萩原さんは語る。
例えば生成AIで自己PRの文章を作成する場合。自分の強み、長所などの要素を複数入力して作ってもらおうとすると、いくつかの要素を抜いて文章を作ってくることがある。
「対策としては、まとめて要素を入力せず、一つ要素を入れて文章を作成し、さらにそこに一つ要素を追加して文章修正、もう一つ要素を追加して文章修正……というように少しずつ要素を加えていき、その都度文章をチェックしていくという方法があります。このほうが、自分が入れたい要素をすべて入れた文章を作ることができます」(萩原さん)
ESの「たたき台」を作成
また、ESの下書きを作成し、それをAIに読ませて指定した文字数まで削った原稿を作ってもらうことで、各社のESに合ったたたき台を作成できる。ただし、文字数のカウントは意外といいかげんで、400字以内と指定しても200字程度まで削ってしまうことがある。「380字以上、400字以内にしてください」など、範囲を指定することが必要だ。
見出しや要約を作る能力も高い。自分の作ったESに見出しをたててもらうことで、面接などで話すポイントをつかむ手助けにもなる。
書いた文章の校正にもAIを活用できる。ポイントは、最初に生成AIに「就活アドバイザー」などの役割を与えること。例えば、次のようなプロンプトを入力するとよいと、萩原さんはアドバイスする。
「あなたは優秀な就活アドバイザーです。以下に貼り付ける文章を修正してください。その際、誤字脱字を見つけたら修正案もつけてください。表記のゆれは調整してください。半角、全角が統一されていない場合、半角に統一してください。文章の末尾は『です、ます』体に統一してください」
面接対策で大きな威力
生成AIは、面接対策で特に威力を発揮する。コミュニケーション能力が格段に向上し、「1人で面接対策ができる時代になった」と萩原さんは話す。
面接対策では、生成AIに面接官の役割を与えることが重要だ。例えば朝日新聞出版の1次面接を想定する場合、以下のようなプロンプトを記入する。




































