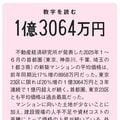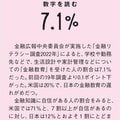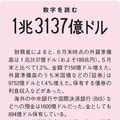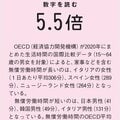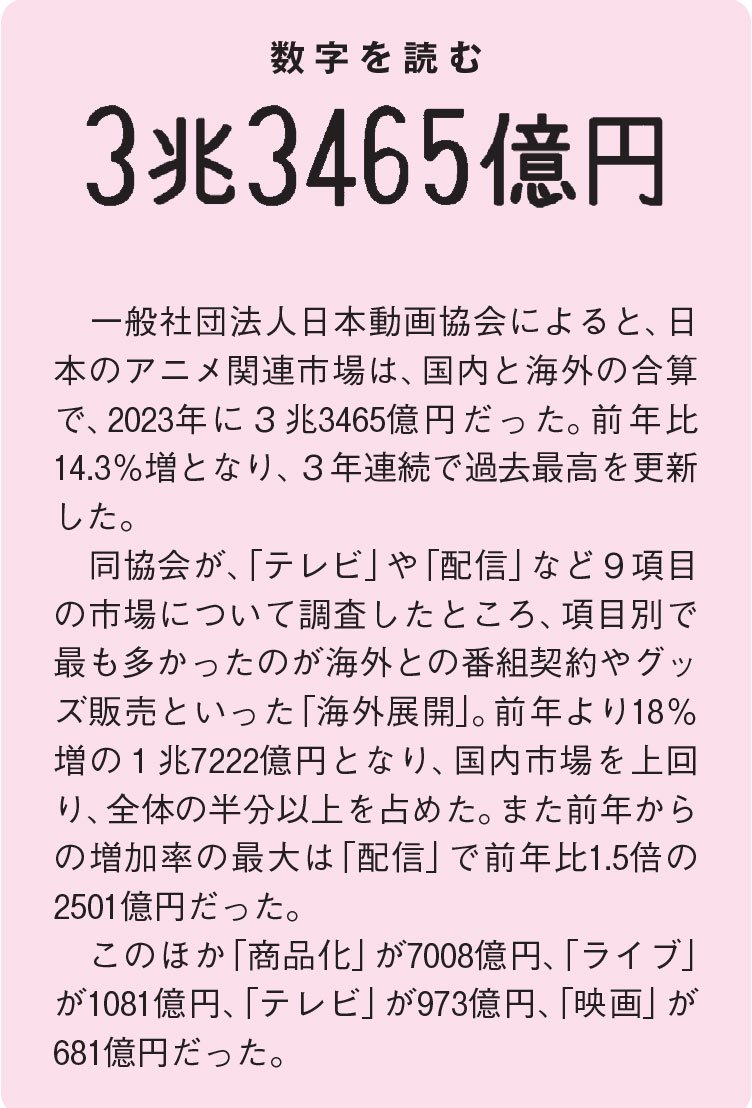
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年8月11日-8月18日合併号より。

* * *
夜10時の映画館でポップコーンを買うのに30分並んだ。人気アニメ「鬼滅の刃」の最新作を初日に見に行ったのだが、その盛況ぶりはすごかった。公開3日間での興行収入55億2千万円は国内歴代1位だそうだ。
この作品の魅力は「分断」を乗り越えようとしている点にあると思う。一見すると、鬼vs.人間の戦いだが、主人公・炭治郎は敵である鬼にも共感し、寄り添おうとする。元々は人間だった鬼たちにも悲しい事情があり、観客も自然と彼らを憎めなくなる。そこに、この作品が多くの人に受け入れられる理由があるのかもしれない。
しかし現実社会はどうだろうか。世の中を見渡せば、分断をあおる情報ばかりが溢れ、一方が他方を批判し合う場面が目立つ。だからこそ、こうした作品が今の私たちに必要なのだと思う。
経済的な視点からも、日本のアニメやコンテンツが世界に広がることは大きな意味を持っている。資源が不足している日本が外貨を稼ぐには、海外が欲しがるものを作り続ける必要があるからだ。かつて日本は、自動車や家電など「メイド・イン・ジャパン」の商品で世界を席巻してきた。しかし、その勢いは今や見る影もない。最近はインバウンド需要に頼る傾向が強いが、観光産業は人手を大量に必要とするため、人材が不足している日本では、他の分野から人を奪って別の問題を生んでいる。
「鬼滅の刃」のような高品質なアニメも、多くの人材を要する産業だが、一度コンテンツを作れば観客がどれだけ増えても追加の労力は最小限で済む。人口が減り続ける日本にとって、コンテンツ産業の存在感は今後ますます大きくなるはずだ。
とはいえ、まだアニメが日本の輸出産業として自動車の規模に及ばないのも事実だ。2024年の日本の自動車輸出は約18兆円であったのに対し、日本アニメ関連の国内と海外の市場合算は約3兆円にとどまる。