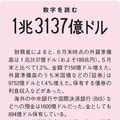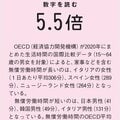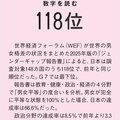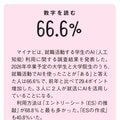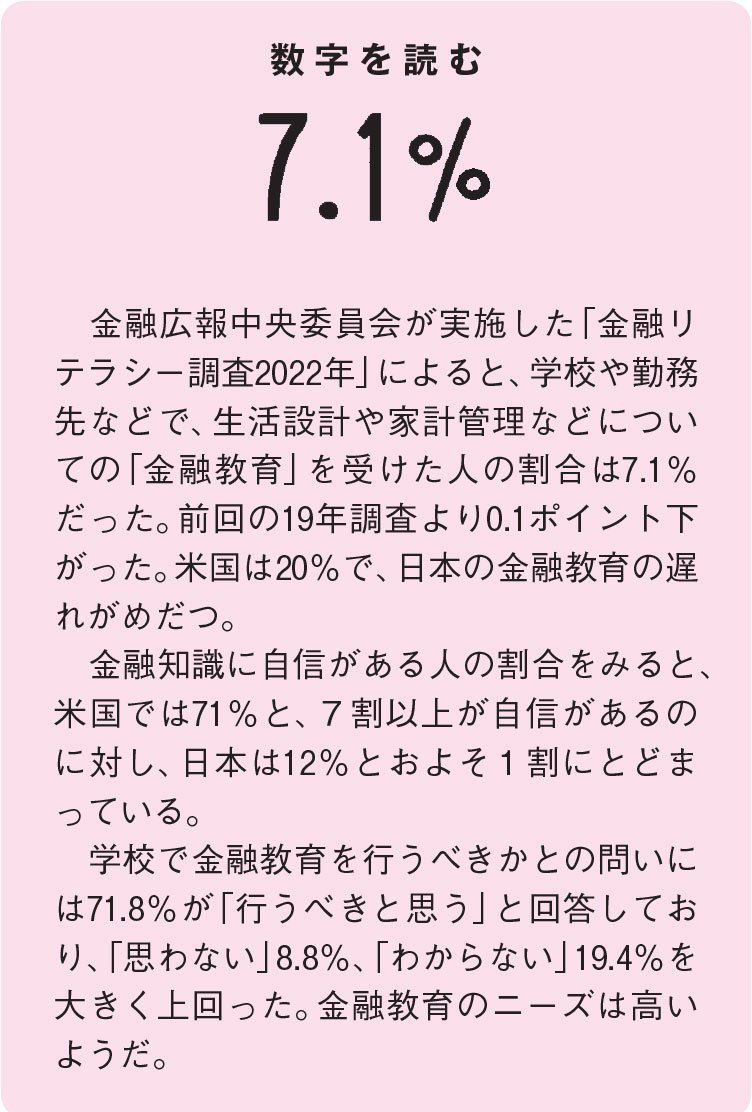
物価高や為替、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年7月28日号より。

* * *
「お父さんお母さん、落ち着いてください!」
最近、子どもを持つ親御さん向けの講演会に呼ばれる機会が増えたが、僕はついそう叫びたくなることがある。金融教育に対して焦りや不安を抱える親御さんが非常に多いのだ。特に多い誤解が「子どもに資産運用の勉強をさせないといけない」というものだ。
ある雑誌の座談会では、未就学児のお母さんが真顔で「港区の幼稚園では株の勉強をしていると聞きました。うちも早く始めないとダメですよね?」と尋ねてきた。冗談のような実話である。「乗り遅れたらまずい」という不安で冷静さを失ってしまっているのだろう。
本来、金融教育はお金の使い方、働く意義、社会の仕組み、家計管理、消費者教育など幅広い内容を含んでおり、資産形成はその一部に過ぎない。だが現状は「投資を学ばせないと子どもの将来が危ない」と煽る風潮がめだつ。
特に問題なのが、金融機関が「高校で資産形成教育が必修化された」と誤解を招く発信をしていることだ。必修である家庭科で金融教育が取り入れられたが、資産運用の話はごく一部だ。それなのに金融機関は「金融教育」と称して生徒向けの投資講座を開催し、将来の顧客獲得を図っている。「未来の日本を守るための金融教育」というテーマでその中身は、「日本の金融資産を守るためにドル投資をしましょう」と学校で教える証券会社まである始末だ。
僕自身「社会的金融教育家」という肩書を使っているが、これは社会学者の宮台真司さんが「金融教育家だとお金儲けを教える人だと思われるから、『社会的』を付けた方がいい」と助言してくれたからだ。実際に金融教育家を名乗る人の多くは資産運用やNISAの話ばかりする金融商品教育家だ。