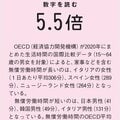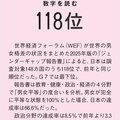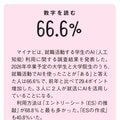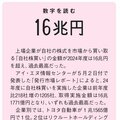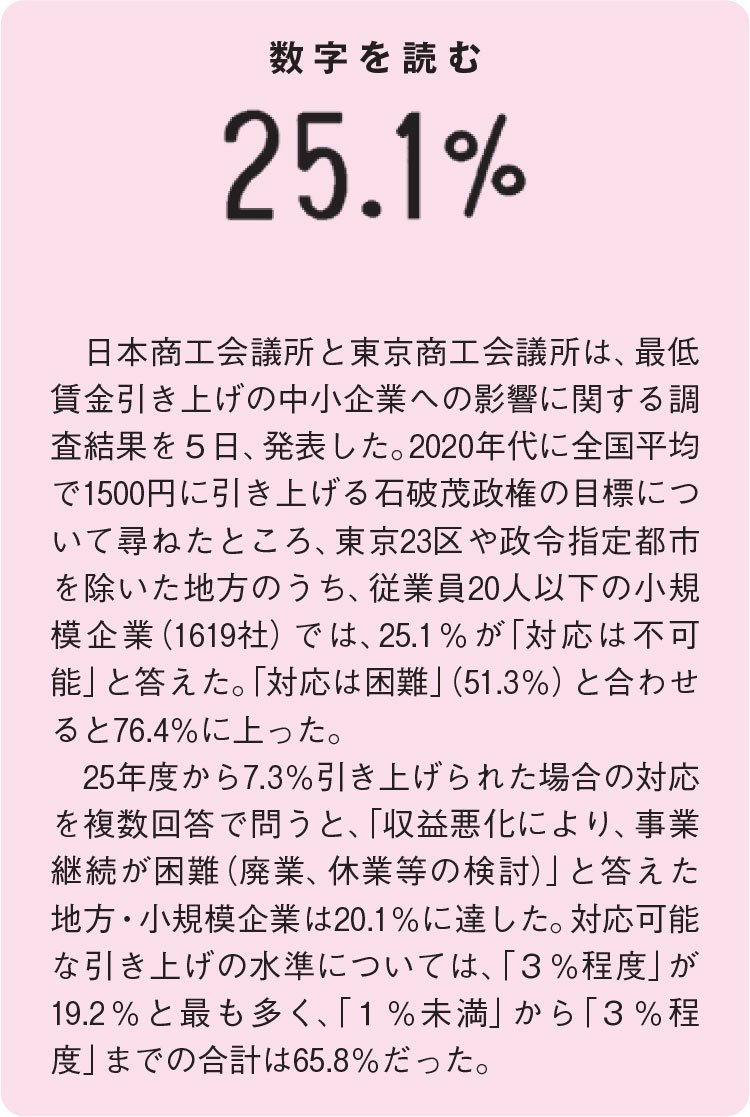
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年3月24日号より。
* * *
社会人になったばかりの頃、有給休暇をすべて使い切ることは許されなかった。制度上は年間20日の権利があったが、周囲の目を気にしてなかなか休みを取れず、半分も消化できないのが当たり前だった。「忙しいのに休むの?」と上司から苦言を呈されることもあった。一方、外国人の同僚は「権利だから当然だ」と平然と休暇をすべて使い切る。その姿を見るたびに、「強制的に休暇を取る仕組みならどれだけ楽だろう」と思ったものだ。権利があっても、合理的に行動するのは簡単ではない。
賃金問題にも同じ構造が見える。合理的に考えれば、同じ労力や能力なら時給が高い企業に移ったほうが得だ。しかし実際には、「あなたに辞められたら会社が困る」「賃金を上げたらお客さんが困ってしまう」などと懇願されると、優しい人ほど待遇の悪い職場に留まり、我慢を続けてしまう。その優しさのおかげで企業や消費者は助かるが、本人だけが不利益を背負い込む形になってしまう。
先日、日本商工会議所と東京商工会議所が最低賃金の引き上げについて全国調査を行った。政府は2020年代に最低賃金を全国平均1500円にする目標を掲げているが、地方の小規模企業の25.1%が「不可能」、51.3%が「困難」と回答した。「最低賃金を上げると地方経済が崩れる」「廃業を検討する」という切実な声も聞かれた。
確かに、市場経済の原理に任せて最低賃金を設定しない方が効率的だという意見もある。そこには、人間は常に自分の利益を優先し合理的に判断するという経済学の前提が存在している。しかし現実社会では、優しさや遠慮という美徳を持つ人ほど合理的に動けず、低賃金から抜け出せなくなる。「あなたが我慢すれば皆が助かる」と言われれば、自分の利益を犠牲にしてしまう人がいる。有給休暇と同様に、法律で「下限」を明確に定めることで初めて、正当な権利を安心して行使できる人がいるのだ。