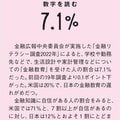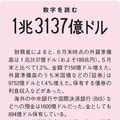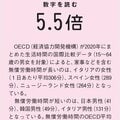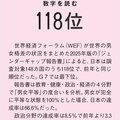2005年を境に上昇基調が続いている。食生活の高級化がすすんでいるという説もあるが、イギリスの22.3%、ドイツの18.9%、アメリカの16.4%と比べると、先進国の中で日本の数値は際立っている。
一般に、エンゲル係数が低いほど、生活は豊かだと考えられている。家計に食費が占める割合が小さいほど、その分を教育費や娯楽、自己投資に回せる余裕があるからだ。
GDP(国内総生産)や日経平均株価は過去最高水準だと言われても、生活実感はまるでついてこない。むしろ、エンゲル係数の上昇こそが、私たちの暮らしが苦しくなっているリアルを映し出しているように思う。
この状態を短期的に緩和するには、備蓄米を放出すればいいとか、円安を抑えればいいといった話が出るかもしれない。だが、長期的には、やはり「自国で何を生産できるか」が重要だろう。
GDPや株価という数字だけを見ていると、どんな分野でもいいから、お金さえ稼げばいいという発想になりがちだ。しかし、本当に自分たちが欲しいものを生産できていなければ、お金だけが増えてもインフレが進むだけで生活の豊かさにはつながらない。
昔は「いただきます」「ごちそうさま」を口にするたび、働く人たちへの感謝を噛み締めていた。そういった気持ちが薄れ、ただお金で買える便利さに頼ってきた結果が、今のエンゲル係数の高さに表れているように思えてならない。
不労所得を増やそうと投資を推進するのも悪くはない。しかしまずは、農家をはじめ、私たちの生活に欠かせないものを提供してくれる“働く人々”が報われる仕組みを整えるほうが先ではないだろうか。値下げばかり求めるのではなく、自国で生産する力を取り戻すことこそ、エンゲル係数を下げる近道になるはずだ。
※AERA 2025年3月3日号