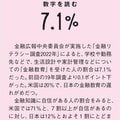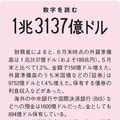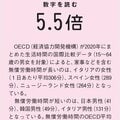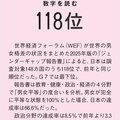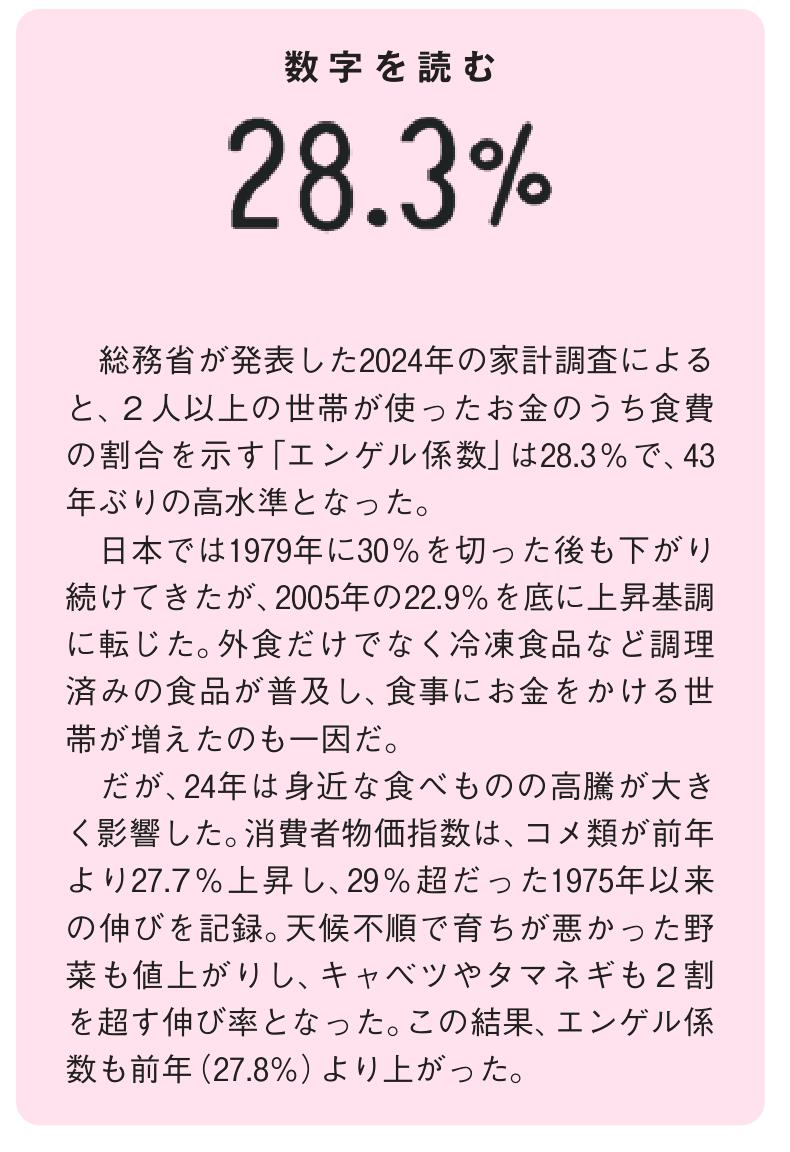
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年3月3日号より。
* * *
昨年末だっただろうか。
「大人が外で『いただきます』と手を合わせるのは恥ずかしい」というSNSの投稿が一部で話題になっていた。こんな些細なことまで非難されるとは、世も末だなと思った記憶がある。
昔は食卓に向かって自然に手を合わせるのが当たり前だった。「いただきます」という言葉には、単なる挨拶以上の意味がこめられていたからだ。米や野菜、魚などの生き物への感謝に加え、その食材を育てたり運んだり調理したりする、あらゆる働く人たちへの敬意があった。
かつて「ご飯一粒でも残すな」と言われたのも、節約のためというより、農家の労力がもったいないという考えが背景にあった。今の日本で農家は減り、食料自給率も38%(カロリーベース)と先進国で群を抜いて低い。日本円が強かったころは海外から食料を買えばよかったが世界経済における日本の地位が下がって円安が進むほど、輸入頼みの食材の価格は跳ね上がりやすくなる。
総務省が発表した2024年のエンゲル係数(2人以上の世帯が使ったお金のうち食費の割合)は28.3%に達し、1981年以来、43年ぶりの高水準だったそうだ。
コメの価格が1.5倍以上に高騰しているとか、キャベツが1玉千円になるなど、食品の値上がりがニュースをにぎわしているが、エンゲル係数の上昇は今年だけの現象ではない。