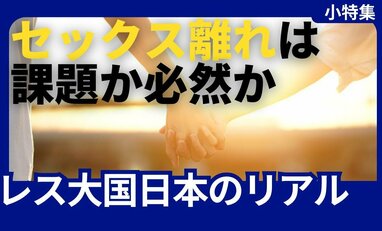以上の評価点を合計すると、生徒たちは最低0ポイント(複数年にわたる活動がひとつもない場合)から最高6ポイント(複数年にわたる活動がふたつあり、その両方で優れた実績を収めた場合)を獲得することになる。
結果は予想どおり、グリット・グリッドで高い評価点を獲得した生徒たちは、「やり抜く力」も強いことがわかった。また、教師たちについても、同様の結果が見られた。
そのあとは、しばらく期間を置いた。
アンケート調査に参加した生徒たちの大半は、高校を卒業後、全米各地の大学に進学した。調査の2年後、1200名の参加者のうち、短大もしくは大学に在籍していたのは、わずか34%だった。そして私たちの予想どおり、グリット・グリッドのスコアの高い生徒たちほど、在籍率が高いことがわかった。
グリット・グリッドで満点の6点を獲得した生徒のうち69%は、2年後も在籍していた。これに対し、6点中0点だった生徒のうち、2年後も在籍していたのは、わずか16%にすぎなかった。
私たちは別の研究でも同じグリット・グリッドを用いて、新人教員たちを対象に、大学時代の課外活動に関する調査を行った。その結果は驚くほど酷似していた。
新人教員のうち、大学時代に複数の活動を最後までやり通し、実績を収めた人は、教職を辞めずに続ける確率が高いだけでなく、生徒たちの学力を向上させる能力も高いことがわかった。
いっぽう、新人教員の過去のSAT(大学進学適性試験)やGPA(成績平均点)のスコアや、リーダーシップ能力に関する面接評価などは、教員としての粘り強さや能力との測定可能な関係は、まったく見られなかった。
●やり通すことで「やり抜く力」を鍛えられる
以上のことを考慮すれば、私がこれまでに示した科学的根拠は、ふたとおりに解釈することができる。私はここまで、課外活動は生徒たちが長期的な目標に向かって、「情熱」と「粘り強さ」を身につけ、育むのに役立つと述べてきた。しかし同時に、課外活動を最後までやり通すことは、「やり抜く力」の強い生徒たちにしかできないと言うこともできる。
このふたつの解釈は矛盾するものではない。それどころか、両方(鍛錬と選抜)の効果が表れている可能性も十分にある。
私がもっとも有力だと思う考え方は、「青年期に何らかの活動を最後までやり通すことは、やり抜く力を要するとともに、やり抜く力を鍛えることにもなる」ということだ。
そう思う理由のひとつは、一般的に、「人は自分の性格に適した状況に引き寄せられるが、その結果、さらにその特徴が強化される」と考えられているからだ。
この人格形成の理論は、ブレント・ロバーツによって「対応原則」と名付けられた。ロバーツはパーソナリティ心理学の第一人者であり、人の考え方や、感じ方や、行動に持続的な変化をもたらす要因を研究している。
ブレント・ロバーツがカリフォルニア大学バークレー校の大学院で心理学を専攻していた当時は、人間の性格は幼年期でほぼ固まってしまい、あとは変わらないというのが一般的な見解だった。
しかしそれから、ロバーツをはじめとするパーソナリティ研究者たちは、何千人もの人びとを対象に数十年にわたる縦断研究を行い、十分なデータを収集した。その結果、人間の性格は、実際には幼年期を過ぎても変化することが明らかになった。