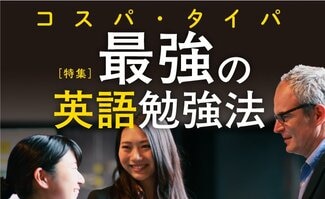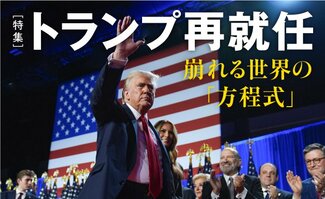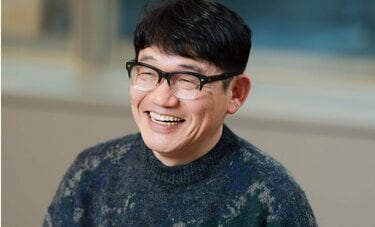鬼を追い払って無病息災を願う「節分」。豆まきなどの行事を楽しみにしている方もいらっしゃると思います。「節分」とは、本来は季節の節目ごとに1年4回あり、暦では「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」の前日を指します。「節分」の由来や風習について解説します。

「節分」とは
今年2025年は2月2日が「節分(せつぶん)」です。
「節分」は、鬼を追い払って無病息災を願う日で、「立春」の前日にあたります。「立春」は年によって変わるため、それに伴って「節分」の日付も年によって変わることになります。
「節分」といえば2月3日のイメージを持つ方が多いですが、今年は立春が2月3日であることから2月2日が節分となります。今年より前に2月2日が節分だったのは4年前の2021年ですが、2021年2月2日の節分はその前をさかのぼると124年ぶりのことでした。また、2月3日以外に節分となったのも、1984年以来、37年ぶりのこととなりました。
本来、「節分」は二十四節気の季節(四季)の始まりにあたる、「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」のそれぞれの前日を指し、年に4回あります。中でも、冬から春に移りかわる「立春」は、一年の始まりとして重要視されてきました。このため、「立春」の前日の「節分」は、現代でいう「大晦日」。一年を締めくくる大切な日でもあります。

「豆まき」の由来
季節の変わり目には「邪気」や「鬼」といった災いを招くものが現れると信じられていました。このため、鬼や邪気を追い払うため、「鬼は外、福は内。」と掛け声をしながら豆をまくのが、「節分」に「豆まき」をする由来と言われています。
「節分」に行われる「豆まき」は、中国から伝わったもので、宮中行事の追儺(ついな)が起源と言われています。追儺(ついな)は、疫病の象徴である鬼を追い払う行事のことで、12月の末日、1月1日の前日に行われましたが、追儺が宮中以外に広まるにつれて、二十四節気における一年の始まりとされている「立春」の前日の「節分」にも行われるようになったと言われています。
日本でいつから「豆まき」が始まったのかは、定かではありませんが、南北朝時代には節分の儀式として、「鬼は外、福は内。」と唱えながら、「豆まき」をしていたことや、公家や武家だけでなく、民間の行事になっていたことが記録された文献が残されています。
なぜ、豆をまくようになったのかについては諸説ありますが、鬼を滅ぼすという意味で「魔(ま)を滅(めっ)する」ことから、「魔滅(まめ)」となり、「豆」につながったと言われています。

「節分」の食べ物
「節分」には「豆まき」を行う行事が主流ですが、「豆まき」のあとは、自分の年の数だけ豆を食べるという風習があります。地域によっても違いがあり、豆の数は年齢より1つ多く食べる所や、煎った豆ではなく、落花生をまく所も多いようです。
「豆まき」以外にも、「節分」に行う風習や食べ物は地域によって様々です。
「恵方巻」を食べる風習は関西から伝わったもので、現代では全国的に広がりました。その年の恵方(縁起がよい方角)を向いて丸ごと1本を黙って食べると願いが叶うと信じられています。なお、今年2025年の恵方は、「西南西」です。
西日本の一部の地域では、イワシを食べ、焼いたイワシの頭とヒイラギの葉を飾るという文化もあります。昔から臭いものや尖ったものには、魔除けの効果があるとされていたためです。
また、四国では、体の中をお掃除するという意味合いでこんにゃくを食べる風習や、山口県や島根県西部では、大きいものを食べると縁起が良いとされ、鯨を食べる風習もあるようです。

「節分」 春が待ち遠しい寒さ
暦の上では「節分」までが「冬」であり、翌日の「立春」から「春」が始まりますが、まだまだ名ばかりの春です。穏やかに晴れた日には日差しに春の訪れを感じられる日も出てきますが、2月はまだまだ寒さが厳しく、雪も降りやすい月です。寒さや雪の情報に注意をする必要があります。
ただ、季節はゆっくりと進んでいます。本格的な春を待ちわびながら、昔から伝えられてきた「節分」の風習を楽しんでみてはいかがでしょうか。