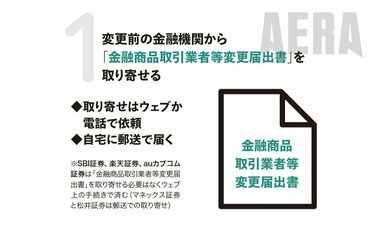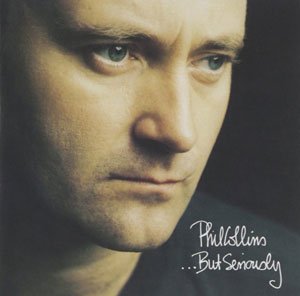



1980年代初頭、完全にアルコールを断つことを決意したクラプトンは、その後、克服に努める過程で自身のレーベルを立ち上げ、あらためて意欲的な姿勢で創作活動に取り組むようになっている。この時期、時代の寵児でもあったフィル・コリンズにプロデュースを依頼し、ライヴなどでも共演したことはすでに書いた。難しい時代を乗り越えるための起用だったのではないかと思うのだが、その一連の仕事への返礼という意味もあったのか、彼が1989年に発表したアルバム『…バット・シリアスリー』にクラプトンはゲスト参加し、素晴らしいプレイを聞かせている。曲は、全米チャートで3位まで上昇するなど、シングルとしても大きなヒットを記録した《アイ・ウィッシュ・イット・ウッド・レイン・ダウン》。
冒頭、コリンズの特徴的なフィルインを受けて、気持ちよくディストーションのかかったクラプトンのギターが斬り込んでくる。やや大げさだが、まさに「斬り込んでくる」という印象だ。それから5分と少々、コリンズのヴォーカルを支え、ときには煽るようにしてクラプトンは力強くギターを弾きつづけていく。ソロと呼べるパートはないものの、終わったあとも、ギターばかりが耳の奥で鳴り響いている。クラプトン寄りの聴き方をしているからかもしれないが、そんな印象。正直なところ、フィル・コリンズはあまり好きなタイプのアーティストではなく、「そこまでしなくても」と思ってしまったほどだ。
コリンズとのつながりでいうと、同時期、やはり彼がプロデュースを手がけたアメリカ人シンガー・ソングライター、スティーヴン・ピショップのアルバム『ボウリング・イン・パリス』にもクラプトンは参加している。曲は、最後に収められた《ホール・ライト》で、ドラムスがコリンズ、ベースとヴォーカルがスティングという、なんとも豪華な顔ぶれだ。クラプトンは終盤、まったく同じ音を約30秒間、47回も弾きつづけるという、誰にも真似できないようなプレイを聞かせている。
スティングの代表曲の一つ《ウィル・ビー・トゥギャザー》にもクラプトンは参加していた。ただし、87年発表のアルバム『…ナッシング・ライク・ザ・サン』収録のトラックからはその音が外されていたのだが、94年発表のベスト盤『フィールズ・オブ・ゴールド』に、未発表ヴァージョンとしてクラプトン入りの《ウィル・ビー・トゥギャザー》が収められている。
80年代にクラプトンが残したセッション・ワークのなかで、個人的にとくに強く印象に残っているのは、トラフィックのドラマー/ヴォーカリストだったジム・キャパルディの『サム・カム・ラニング』。88年発表のこのアルバム、彼は《ユー・アー・ザ・ワン》と《オー・ロード、ホワイ・ロード?》の2曲でギターを弾いているのだが、後者にはジョージ・ハリスンも参加。神に語りかけるキャパルディの歌を、力強く、しかも叙情的なプレイで支えている。 [次回10/28(水)更新予定]
 大友博
大友博