術後は神経麻痺(まひ)による声のかすれ(嗄声、させい)がありリハビリテーションもおこなった。放射線治療を2度施行し、その後は再発なく現在にいたっている。甲状腺を全部摘出したため、現在は毎日甲状腺ホルモンの摂取をしているものの、それ以外に症状はなく、仕事にも復帰している。
がんの発見から3年が過ぎた。
「腫瘍内科医として、多くの患者さんを診療してきた経験もあって、もともと普通の人よりは死は身近なものでしたが、自分ががんになったことでその存在がリアルになったことは確かですね。50歳を前にしてのがんは確かに少し早いですが、それは特別なことでもないと考えています」
医師としての考え方には多少の変化はあったという。
「後悔がないように、できることを淡々とやっていこう、という思いが強くなりました。以前よりがん患者さんの気持ちがわかるようになったし、それだけに患者さんの期待に応えたいという思いも強くなった。その半面、私自身の力が抜けたのも事実です。『いい医師でなければ』と気張る姿勢がなくなったことは、医師としてよかったんじゃないですかね」
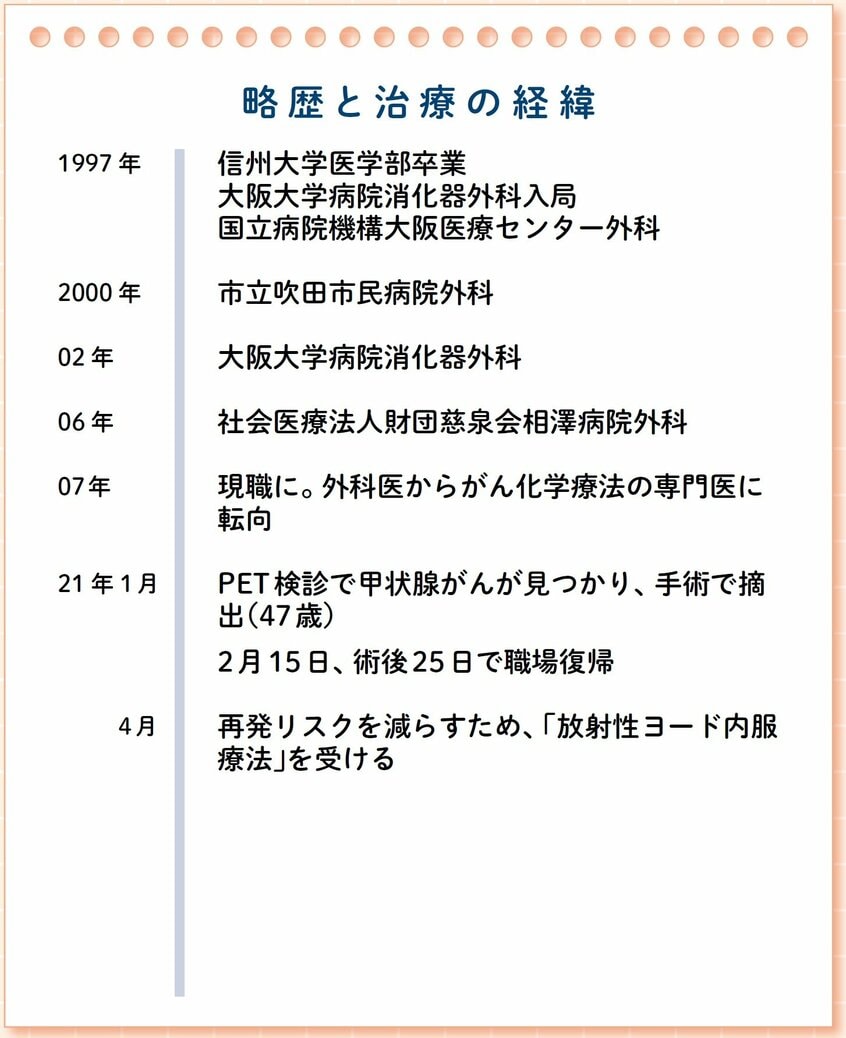
がん相談支援センターで不安な気持ちを話して
中村医師の言葉から、「知識の強み」を感じ取ることができる。正しい知識があればこそ、がんと告知されても冷静さを失うことなく動けたわけで、その「迷いのなさ」は医療者ならではの利点なのかもしれない。
これに対して中村医師は「医師だから特別――とは考えないでほしい」と訴える。
「がん相談支援センター」を設置する病院は全国で増えており、各自治体のホームページからも確認できる。がんという病気について、あるいは治療について不安があるときは、センターに相談すれば、専門のトレーニングを積んだ相談員が病気の状況に応じた対応をしてくれる。しかもその相談は、その病院にかかっていない患者も受けることが可能だ。
「がんと診断されてもあわてず、医療従事者と相談し、不安なことがある場合にはがん相談支援センターに連絡してほしい」
そうした情報を持っているか否かで、患者の行動や安心感は大きく左右される。少なくともがん治療において、正しい知識や情報を持っていることがデメリットになることはないはずだ。
(取材・文/長田昭二)
※週刊朝日ムック『手術数でわかるいい病院2024』より
こちらの記事もおすすめ がん闘病中の医療ジャーナリストが、2度がんになったがん治療医を取材 「経験は診療姿勢も変えた」






































