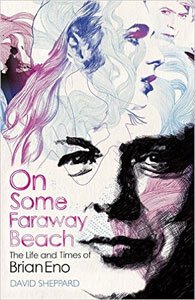
『オン・サム・ファラウェイ・ビーチ:ザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・ブライアン・イーノ』デイヴィッド・シェパード著
●第6章 ベイビーズ・オン・ファイアーより抜粋
ブライアン・フェリーは1973年の初夏、さまざまな意味で限界に達していた。ロキシー・ミュージックは6月に、ヨーク・ミュージック・フェスティヴァルのサタデイ・ナイトで主役を務めることになっていたが、フェリーはショーに先立って、キーボードとヴァイオリンの神童エディ・ジョブソンに接触し、ロキシーに加入した場合の役割について話をしていた。
プログレッシヴ・ロック・グループのカーヴド・エアを脱退したばかりのジョブソンは、偶然にもフェリーの妹の、大学の女友達の弟だった。フェリーは、バンドのメンバーに何も知らせずに、ティーンエイジャーの天才ミュージシャンをヨークに招いた。ジョブソンは、通行証を握りしめて、ロキシーのロード・クルーに紛れ込み、イーノを間近で研究した。
ロンドンからヨークに向かう途中、フェリーは、最新版の音楽紙を横目に見た。ほとんどの音楽紙が、イーノを取り上げ、熱筆をふるっていた。そして、ヨークの会場に到着すると、報道価値のある “ライヴァル” が、ジャーナリストにさらに愛想をふりまき、狂喜させていることに気づいた。
フェリーは、怒りのヴォルテージを上げたが、イーノは午後、ポーツマス・シンフォニアの演奏に参加するため、足早に出かけた。それは、フェリーにとって悪夢のようなものだった。語るに足る曲を決して書いてはいないイーノが、テープ・レコーダーを操ることによって、バンドの中で唯一無二の存在になり、その姿が、常に彼の視界に入った。
ロキシーがその夜、ステージに出ると、観客はざわめき、今にも興奮を爆発させようとしていた。そして、イーノの羽根が揺れ、シンセサイザーが発信音を出すたびに、割れんばかりの大喝采をした。拍手喝采はまもなく、チャントにエスカレートした。フェリーが、≪ビューティー・クイーン≫を歌いあげる間、「イーノ、イーノ、イーノ」というサッカーの応援さながらのコールが、次第に高まり、やがてフェリーのヴォーカルを完全にかき消した。
イーノは、彼自身が大騒ぎの引き金になっていることを実感し、潔くステージを去り、客席を静めようとした。だがそれは、逆効果を招いた。彼は結局、持ち場に戻り、身ぶり手ぶりで「静かにしてくれ」と伝えざるをえなかった。フェリーの屈辱感は、誰の目にも明らかだった。
アンコールの後、フェリーは舞台の袖で怒りを爆発させ、マーク・フェンウィックとデイヴィッド・エントーヴェンに、イーノと同じステージには二度と立たないと言い放った。
フェリーが現在、修復不可能に陥った不和の原因は、音楽的な問題以上に、記者の介在にあったと明言する。
「クリエイティヴな衝突は、実際すばらしいことだ。それによって、さらに向上し、進化する。だが、ブライアンと私の間にあった軋轢は、部外者の影響によって、つまり私たちを対立させるジャーナリストによって、激しさを増した。ジャーナリストが誰一人いなければ、ブライアンと私は、まだ一緒に活動していたことだろう。とにかく、『ブライアンがブライアンに嫉妬する』というような記事が氾濫していた。たしかに、火のないところに煙は立たない。だが、それを大げさに書き立てられたんだ」
フェリーはヨークの一件の後、エディ・ジョブソンをイーノの後任として加入させるという意思を、露骨に態度に出した。彼自身、「私がブライアンを実質的に締め出した」と認めている。だが、憤激しつつも臆病なシンガーは、やはり逡巡し、面と向かって決着をつけることができなかった。その結果、ロキシーの内部には、重苦しい空気が漂った。
フェリーは、逃避した。彼はまず、ソロによるカヴァー・アルバム『ディーズ・フーリッシュ・シングス』のレコーディングに専念し、その後、ジェット機でコルフ島に向かい、休暇をとった。そして、イオニアの太陽を浴びながら、マネージメントを行うEGが、腹立たしいイーノを追い払ってくれればと思った。
イーノは少なからず、フェリーの心情を察していた。彼が1977年に、イアン・マクドナルドに語っている。「ブライアンの気持ちはよくわかった。情感をこめて、あのすばらしい曲を歌う最中に、ホールの後方から馬鹿な客に、『イーノ!』とわめかれるんだからね」
だが当時、イーノは依然として、多元的なロキシー・ミュージックに無限の可能性を感じ、アプローチを変えて体良くブライアン・フェリーのバック・バンド化することには抵抗を覚えた。
「ロキシーに関して純粋に楽しく面白いと思ったのが、バンドの多様性だった。実際、さまざまなスタイルの音楽表現の中で、常に触発しあい反応しあうという緊張感があった。その緊張感を助長したのが、私だと思いたい。
私はいつも、言っていたんだ。バンドをこのジャンル、あのジャンルに方向づけて、洗練させるべきじゃないと。ロキシーは、緊張感のある相互作用によって、そのバランス次第で、どんな方向にも向かいうるユニットだし、だからこそ、演奏が、極端に荒くなる場合もあるが、全体としては、面白い。私たちは、それを認める必要があるとね。ブライアンと私が揉めたのは、彼がこの点に同意できなかったからだ」
『On Some Faraway Beach : The Life and Times of Brian Eno』By David Sheppard
訳:中山啓子
[次回8/24(月)更新予定]
■参考:オススメ・ライヴ情報 第47回 ペンギン・カフェ・オーケストラとブライアン・イーノ(文・小熊一実)
































