



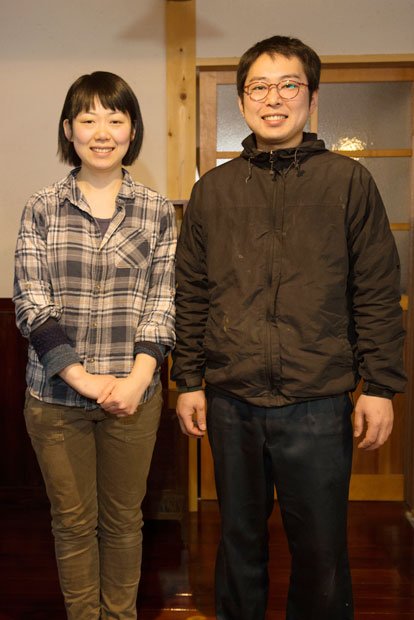

漆器は、木製の生地に漆を塗り重ねるモノ。そういう思い込みがありました。
丸嘉小坂(まるよしこさか)漆器店の「百色(ひゃくしき)」は、「漆らしさを、使いやすく楽しいものに昇華させたい」という考えのもとに生み出された、漆硝子です。透明なガラスの器に、ひとつずつ、外から漆で模様をつけます。漆が器の外側に塗られているので、料理が盛られる側、箸が触れる内側はガラス面になっています。金属製のスプーンやフォークも気兼ねなく使え、油ものも盛りつけできます。中性洗剤を使用したスポンジ洗いもでき、より日常使いに適しています。
「百色」は、かつて万華鏡が「百色眼鏡」と呼ばれていたことから、万華鏡のように、のぞき込む楽しさにあふれた器を作りたいと名付けられました。日本の伝統的な色や文様を意識しながら、非常に新鮮で、広がりや奥行きを感じさせる、あたかもこれからの漆産業の明るい未来を映し出すかのような、宇宙的な模様になっています。漆は生き物。エイジングも念頭に置き、味のある絵付けにこだわっています。絵付けの後、漆がガラスから剥離しないように焼き付けをするのですが、これが技術的には一番の難題だったそうです。そんな難題も乗り越える、作り手の希望や夢、気概や熱が感じられる商品です。
この百色を生み出したのが、丸嘉小坂漆器店3代目のコサカレオさん。まっすぐな方で、言葉を探しながら、じっと目を見て語り掛けてくれます。僕がかなり面白い冗談を言っても、あまり笑ってくれません(泣)。その姿勢はモノヅクリにもきちんとあらわれていて、一つずつ丁寧に作られた商品は、どれも少しずつ表情が違い、選ぶ楽しみがあります。
百色のベースとなったのは、実はコサカさんのお父さんが20年前に作った「すいとうよ」というブランド。漆硝子の先駆けです。百色は、息子のレオさんが、若手デザイナーとの交流の中で、より日常生活に溶け込みやすい漆表現を追求して生まれました。
得てして既存の業界に新しい風を吹き込む人は、他業界での経験が背景にあるもの。新鮮な目で現状を見て、こうすればいいんじゃない?という素朴な発想が、新しいモノヅクリを生み出します。コサカさんも、実は工場を継ぐ気はなく、学校を出た後に、医療事務のサラリーマンを2年ほどやっていたそうです。そんな時、ふと見た仕事に打ち込むオヤジの姿に、初めてググッと心が動いた。自分たちを育ててくれた、その技を引き継いでいきたい、自分もやりたいと思った。そう話してくれたコサカさん、やっぱりあんたも熱い男だね!
コサカさんには、近いうちに作り手と使い手の出会いの場・日本百貨店に来てもらって、その熱い思いをお客様たちに伝えてもらいたいと思っています。海外での販売も一緒にできるとイイネ!
いつかは使いたい浄法寺漆器。
まずは漆に触れることから、マルチロール漆。
そして漆の新しいカタチ、百色。
それぞれ味わいの異なる漆器を、ぜひ実際に使って、漆の美しさ、肌ざわりや口当たりの良さ、次第に生まれる艶、そして日本の伝統と未来を感じてもらいたいと思います。


































