
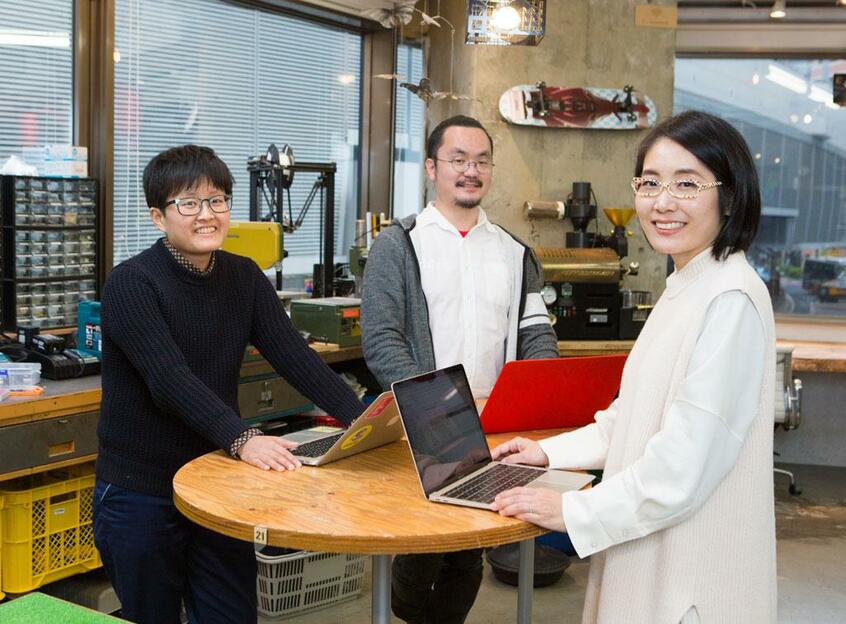
#KuToo運動が大きな広がりを見せた背景には、オンライン署名サイトChange.org(チェンジ・ドット・オーグ)の存在が大きい。声なき声を社会に問う手段として大切な役割を担っているが、なぜ日本では声を上げた人が批判されやすいのか。AERA 2019年12月30日-2020年1月6日合併号は、Change.orgの「中の人」に取材した。
【写真】Change.org JAPANを運営するメンバーはこちら
* * *
#KuTooへのバッシング然り、声をあげた人が叩かれるのは一体なぜなのか。日本ではことさら「声をあげる資格」を問いたがる節がある。環境活動家のグレタ・トゥンベリさんに対して「こいつは何様のつもりだ」などという罵倒が続くのもその典型だろう。
チェンジでキャンペーンを立ち上げ発信者となるのは、何様でもない、一人ひとりだ。地位や、人脈や、知名度や、影響力があるわけでもない。
署名を受け取ってもらうことも増えてはきたが、ネットというだけで“顔のない不特定多数のいたずら書き”と思われてしまうこともまだまだ多いと武村さんたちは課題を感じている。
それはSNSでの中傷や攻撃的な書き込みと地続きの問題ではないかとChange.org Japanのカントリー・ディレクター、武村若葉さんは指摘する。書き込みや署名のクリックの向こうには人がいる、ということがもっと意識されるべきだと。
「ネットだからなんでも言っていいわけじゃないし、クリックする一人ひとりが顔も名前も持っている。自分がなぜその問題にコミットするのか、誰にでもパーソナルストーリーを語る権利はあります。“何様”なのかと言われたら、“わたし様”だよ、ってそう一つずつ言い返していくしかないのだと思います」
一人称視点でも社会の問題は語れるし、多くの人の共感を得ることができる。チェンジでの数々のキャンペーンで、それは証明されてきた。
「声をあげること、他人の物語に心を動かされることが日常的な光景になれば、人々の無力感は変容するはず。社会は時々は変えられるんだ、と多くの人に伝えていきたい」(同社キャンペーン・サポーター遠藤まめたさん)
「中の人」たちは、一人称のストーリーの力を信じている。(編集部・高橋有紀)
※AERA 2019年12月30日号-2020年1月6日合併号より抜粋




![AERA (アエラ) 2019年 12/30-1/6 合併号【表紙:木村拓哉】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51rUSkm3F-L._SL500_.jpg)


































