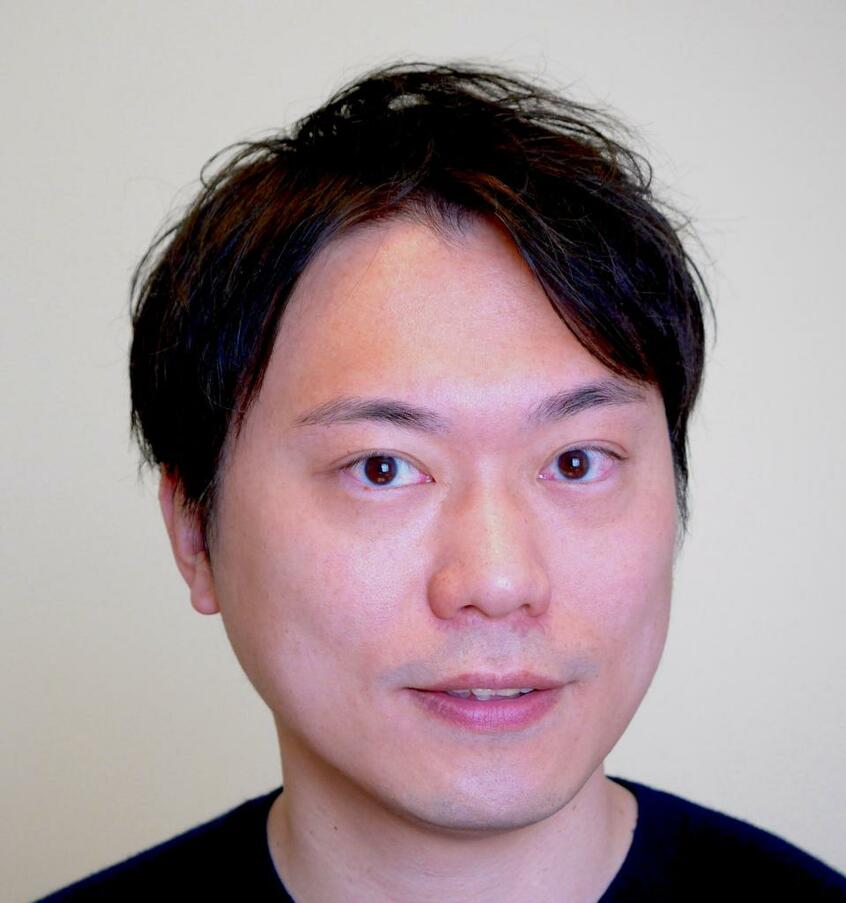
■若い頃の日焼けや暴飲暴食、体が記憶し老化引き起こす
早野さんらは今回、生後4~6カ月のマウスのDNAを短期的に損傷し、長期の経過観察を行ったところ、DNA損傷は修復され、DNA配列に異常は観察されなかった。その一方、認知機能や筋力、骨密度、視神経などの身体機能が低下していることが分かった。
「若い時期のDNA損傷はDNA配列ではなくエピゲノム変化として記憶され、細胞や臓器のエピゲノム情報を消失させることで老化の速度やタイミングを制御し、長期的な身体機能を低下させることが示されました」
早野さんはこう続ける。
「人間も若い頃に日焼けしたり、暴飲暴食したりするようなストレスを体は覚えていて、それが中年期や更年期にさまざまな疾患や老化現象を引き起こします。これはエピゲノムの変化によって遺伝子が適切に働かなくなり、臓器や筋肉、骨、目や耳などの老化が加速するためと考えられます」
エピゲノムの解析技術が進めば、将来、どんな病気にかかりやすいか、どんな速度で老化が進むのかを早期に個別診断し、治療に役立てることも期待されるという。
今回の研究では、京都大学iPS細胞研究所名誉所長の山中伸弥教授が発見した、細胞の初期化を誘導する四つの遺伝子(山中因子)の中の3遺伝子を導入することで、エピゲノムなどが改善されることも分かった。生年月日で決まる「暦年齢」よりも、生体を構成する細胞や組織の機能に応じて定まる「生物学的年齢」がものを言う時代がすぐそこまで来ている、と早野さんは言う。
「個別の生物学的年齢を正確に識別する技術を確立した上で、生物学的年齢を若返らせることも山中因子を使えば可能になると思います」
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2023年2月27日号より抜粋






































