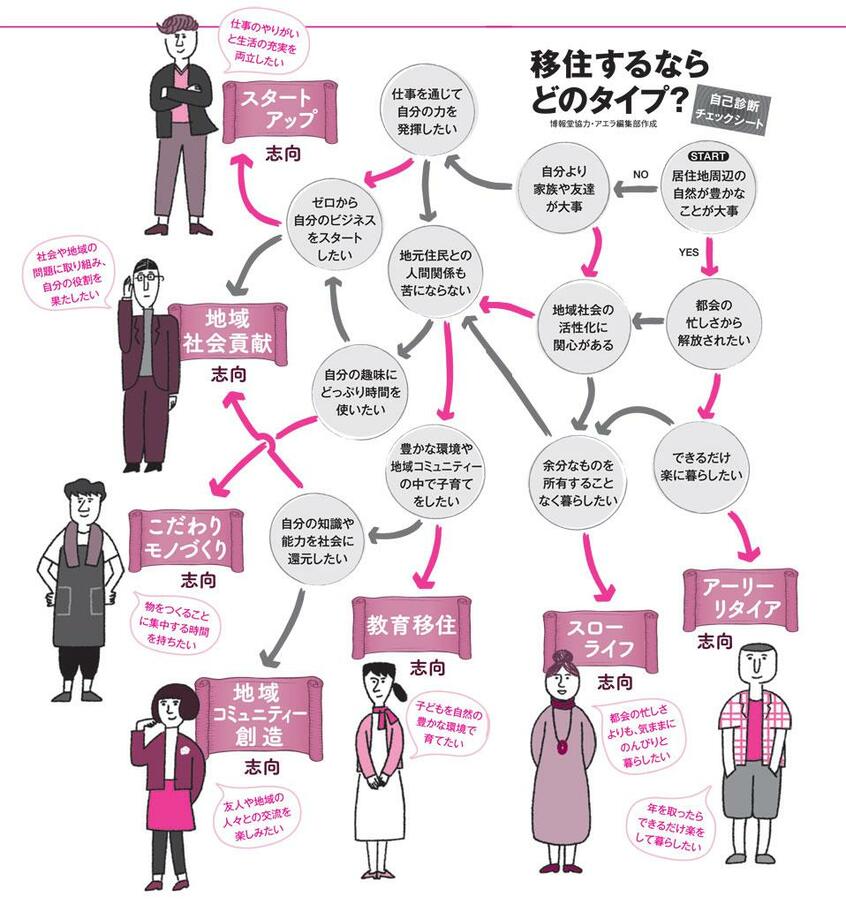
インターネットや本などで移住情報を得ることもできるが、重要なのはいかに移住前に「地元の人」と接点を持てるかという点にある。
移住者の志向や動向に詳しい博報堂の鷹野翔平ディレクターは、移住者の追跡調査をした経験から、移住情報を得る重要なタッチポイントとして「現地の居酒屋」を挙げる。
「居酒屋のよいところは人と人の出会いの場になっていることです。移住先として検討している段階で、観光ついでに現地で馴染(なじ)みの居酒屋をつくっておけば、耳よりの住宅情報などを店主や常連客を通じて、リアルタイムに得ることもできます」(鷹野ディレクター)
一部の自治体で実施している「お試し移住」や体験ツアーも積極的に活用したい。
先駆的な取り組みとして注目されているのが、兵庫県の神戸市、芦屋市、洲本市、淡路市の4自治体が広域連携し、移住者受け入れに取り組む「島&都市デュアル」だ。
淡路島内の洲本、淡路市と、阪神間の都市部にある神戸、芦屋市の4市は60キロ圏内。明石海峡大橋を使えば気軽に行き来できることから、実際の生活圏として「都市の文化」と「島の自然」の魅力をセットで堪能できることをアピールする戦略だ。4市の移住体験者と交流できるツアーも定期開催している。
東京在住者の強い味方になるのは、NPO法人が運営する「ふるさと回帰支援センター」(東京・有楽町)だ。東京・大阪を除く45道府県の自治体と連携して地域の情報を提供し、都市と農村の橋渡しによって地方の再生、活性化を目指している。「地方暮らし」に関するパンフレットや資料を常設しているほか、各地域の移住相談員が情報を提供し、常時相談に応じている。セミナーも年に約500回開催するなど首都圏の移住希望者には必須の窓口といえる。(編集部・渡辺豪)
※AERA 2018年10月8日号より抜粋








































