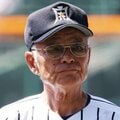福田淳一財務事務次官のセクハラ疑惑が浮き彫りにしたのは、財務省の「トンデモ」対応だけではない。被害者が声を上げにくい、日本社会の根本治癒も不可欠だ。
事務次官が女性記者に対するセクハラの事実を認めないまま辞任表明した翌日の4月19日。5人の弁護士が財務省に署名の束を提出した。
「この30年は何だったのか。高級官僚が学んでいなかったことがわかり、この国はどうなるんだろうと思いました」
1989年に日本初のセクシュアルハラスメント裁判にかかわった角田由紀子弁護士はこう嘆いた。
事務次官のセクハラ疑惑を受け、財務省は「事実関係の解明は困難」として被害女性に名乗り出て調査協力するよう要請。これに対し、同省に調査方法の撤回を求めるネット署名を弁護士有志が呼び掛けたところ、2日余りで3万5千筆の賛同署名が寄せられた。
●時代錯誤の調査手法
署名提出後の会見で、先の角田弁護士ら呼び掛け人の弁護士が口々に発言。署名の輪が広がった背景について早田由布子弁護士は「財務省と市民の認識のずれ」を表すもの、と評した。
18日の財務金融委員会。財務省の矢野康治官房長は「(被害女性が)財務省でなく、弁護士さんに名乗り出て、名前を伏せておっしゃることが、そんなに苦痛なことなのか」と答弁した。
こうした財務省の認識はいかに時代錯誤か。太田啓子弁護士は「被害者をあぶり出すような手法は許されない」とし、財務省の顧問弁護士事務所が調査主体になる不当性を訴えた。
「顧問弁護士は依頼主に報告義務があり、中立公正な役割を果たしようがないのは常識。日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインにも、顧問弁護士は『利害関係を有する者に該当する』と明記されています」
職場でのセクハラの相談対応に関して厚生労働省は「使用者は、相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずる」などの指針を提示。人事院規則も「関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守」することを明示している。