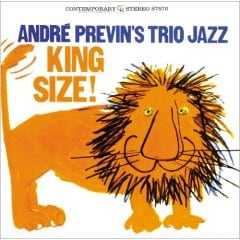
アンドレ・プレヴィンのジャズ・ピアノをCDでよく聴く。
こういうと、コアなジャズ好きは、眉をひそめようか。「あんなの、ほんとうのジャズじゃない。曲たちをなぞっているだけだ」というような声も、聴こえて来そうな気がする。
一般に、プレヴィンの名は、クラシック音楽の指揮者として知られている。ヒューストン交響楽団にはじまり、世界中のオーケストラで音楽監督をつとめてきた。ウィーン・フィルやベルリン・フィルでも、しばしばタクトを振っている。
そして、そういう身でありながら、時にはジャズのステージもこなす。レコーディングも行っている。アカデミックな世界でも位人臣を極めながら、ジャズの世界にも降りてくる。
そんな振る舞いが、いかにもジャズを見下しているように映るのだろう。息抜きのために、ジャズで羽を伸ばしている。アカデミックな大物が、骨休めのため温泉へつかりに来る。その温泉と同じようにジャズは扱われていると、ジャズ一筋の人には見えてしまう。彼らが反感を抱くのも、まあやむを得まい。
しかし、そのリラックスした、肩の凝らない演奏が、私にはいいのだ。コアなジャズ好きが息抜きでけしからんという、そこのところに、私は魅力を感じる。
問題をつくってやるというような野心はない。力をぬいて気心の知れたミュージシャンたちとここちよい音を紡ぎ出す。洗練された、小粋な、都会的に響く音楽を奏でてくれる。そこが、私にはたまらない。自分も温泉で体をやすめているような気分になる。
ジャズ・ピアノのキース・ジャレットが、ヘンデルなどの録音に取り組んできた。だが、クラシックを弾くキースに、普段の伸びやかな音はない。整ってはいるが、どこか縮こまっているように響く。アカデミックな音楽を前にして、ややこわばっているかなと思う。
比べれば、プレヴィンの脱力感が、私には好ましい。息抜きでけっこうだ。いや、息を抜いたところに成り立つジャズの味わいも、間違いなくあると考える。
いわゆるジャズマンには、なかなか醸し出しえない。クラシックの人が、気持ちを和ませた時に育みうる、そんなジャズの音があってもいいし、私はそういう音が好きである。
プレヴィンは、もともとポピュラー畑の音楽家であった。1940年代には、ハリウッドで映画音楽の作曲を手がけだしている。1950年代からは、ジャズ・ピアニストとしても、活躍しはじめた。
だが、1960年代の後半には、指揮者を志し、アカデミックな世界へ移っている。そして、そちらで成功を収め、二十世紀の終わりになって、ジャズの世界へ帰ってきた。偉くなり仰せた人が、しばしば故郷を訪れるようになったということか。
その意味で、プレヴィンは、ふたつの世界に通じている。なかなか難しい音楽的な越境を、軽やかにこなした人であったと言ってよい。
そう、クラシックの腕達者なら、誰でもできるというわけではないのである。フリードリヒ・グルダのジャズは、やはりジャズとしては聴きづらい。ジャン・イヴ・ティボーデもうまいが、ちょっとどうかなと思う。やはり、プレヴィンはその点で出色の音楽家ではなかろうか。
かつて、ジョージ・ガーシュインという作曲家がいた。二十世紀初頭のアメリカで、たくさんのヒット曲をこしらえたことで知られている。
アカデミックな音楽にも、志を抱いていた。ラヴェルに師事を願い出て、断られたというエピソードもある。「二流のラヴェルになるより、一流のガーシュインでいて下さい」と、さとされたらしい。
だが、志はなくならず、そちらの面の曲も書いている。「ラプソディー・イン・ブルー」は、その代表的な作品である。そして、この曲は、クラシックのレパートリーに組み込まれている。
「ラプソディー・イン・ブルー」の演奏では、プレヴィンの名が高い。ジャズ育ちだということで、はまり役とされている。しかし、プレヴィンの「ラプソディー・イン・ブルー」は、やや表情が硬い。ジャズの風の軽みは、避けられている。そこが残念だという向きも、ないではない。
だが、プレヴィンは、そこを狙っていたような気がする。クラシックに憧れ、しゃっちょこばったガーシュインを再現する。そのために、わざと硬めな構えで臨んだと考えるが、どうだろう。


































