
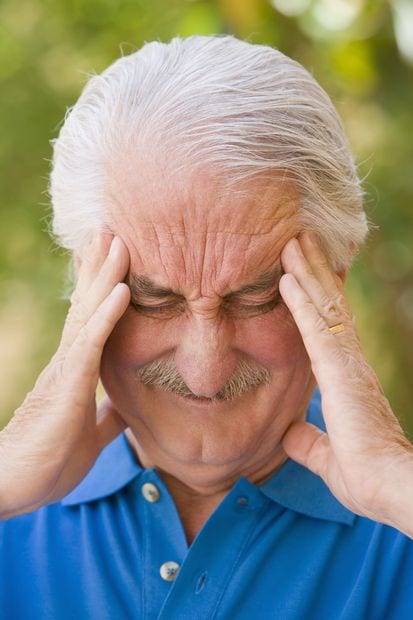
西洋医学だけでなく、さまざまな療法でがんに立ち向かい、人間をまるごととらえるホリスティック医学を提唱する帯津良一(おびつ・りょういち)氏。帯津氏が、貝原益軒の『養生訓』を元に自身の“養生訓”を明かす。
* * *
【貝原益軒養生訓】(巻第八の5)
今の世、老(おい)て子に養はるる人、わかき時より、
かへつていかり多く、慾(よく)ふかくなりて、子をせめ、
人をとがめて、晩節をたもたず、心をみだす人多し。
養生訓では巻第八の前半に「養老」という題名をつけて、老人の養い方や老人の振る舞いについて語っています。そこでは27項目にわたり、老いに対する考え方を披露しています。その一つはこういうものです。
「いまの世は、老いて子に養われる人に、若い時より怒りが多くなり、欲が深くなって、子をせめ、人をとがめて、晩節の節度をたもつことができずに、心を乱す人が多い」(巻第八の5)
なかなか厳しい見方ですが、これに対する子どもの対応として、こう説いています。
「子はそういうものだと思って、父母が怒らないように、日頃から気をつかい、慎重になるべきである。父母を怒らせるのは子としては大いなる不孝となってしまう」(同)
この老いて乱れるというのは、ひとつには、子に養われるというところに起因しているのではないでしょうか。以前にも紹介しましたが(6月30日号)、養生訓の研究家として名高い立川昭二先生が「人生の幸福は後半にあり」という益軒の慧眼について、老いの豊かさを支えるのは、一に生活費、二に健康、三に生きがいであると補足しています。老いても生活費を自分で確保できることが、実は心の平穏にとっては重要なのかもしれません。
人生の後半を見事に生きた人物として立川先生が著書『足るを知る生き方』(講談社)で紹介しているのが神沢杜口(かんざわとこう・1710~95)です。益軒の晩年期に生まれた杜口は益軒とは面識がなかったでしょうが、その影響は強く感じられます。


































