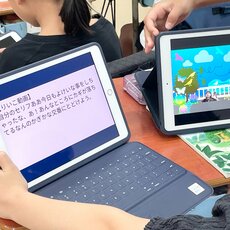「孺悲(じゅひ)、孔子に見えんと欲す。孔子、辞するに疾(やま)いを以(も)ってす。命を将(おこな)う者、戸を出(い)づ。瑟(しつ)を取りて歌い、之(こ)れをして之(こ)れを聞かしむ」(陽貨第十七)
「孺悲という人が、孔子に面会をもとめたが、孔子は病気だといって会わなかった。取次の人が断りを伝えるためにドアを出ていくと、すぐ瑟(しつ=琴のような楽器)を引き寄せ、歌声がきこえるように歌をうたって、孺悲の耳に入るようにした」という意味です。
孺悲という人がどのような人か分かっていません。でも直接、孔子を訪ねてきた人だったので、相当の身分の人だったのでしょう。一説では、魯(ろ)の国王・哀公の依頼で、孔子から冠婚葬祭の礼儀作法を学んだ人とも言われています。この人物があるとき、孔子に面会を希望したが、孔子は彼に会いたくなかった。それで病気だといって断ります。でも実際は病気ではないことを知らせ、「会いたくないのは拒絶させる原因が孺悲のほうにある」と婉曲に知らせて追い払ったのです。
忖度、同調圧力、無責任主義……日本の集団は息苦しいものです。自分の意見や行動基準を保つ訓練をしていないと、集団のものの見方にすぐ感染してしまいます。どうぞ、相談者さんと妻は、周りに影響を受けないでください。PTA役員を引き受けたのだとしたら、自分たちにもっと自信を持って、忖度や付和雷同はやめて、思っていることを言えるよう、できない仕事はNOと断れるようにしましょう。そうすれば、道は必ず、明るく開けるはずです。
【まとめ】
社会を変えて、よりよい社会を創るために必要なのは、「和して同ぜず」という力
著者 開く閉じる