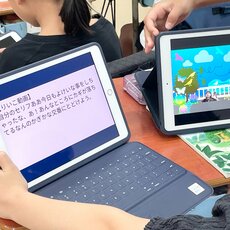「発達障害の子は生きづらさを抱えストレスフルですから、ストレスがかかわる摂食障害を発症するリスクは当然大きくなる。こだわりが強いために特定の食べ物を口にしないなど、ダイエットをエスカレートさせてしまう側面もあります」
と河合医師。摂食障害の症状で来院した子を診察した結果、発達障害がわかることもあると言います。「摂食障害の診断を受けた人の約5%は発達障害を持っていた」という研究結果も報告されています。
将来、低身長や不妊になるリスクも
小学生の6年間はからだも心も大きく成長します。摂食障害になると成長の遅れ、栄養不足、骨密度の低下など、健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そして現在の健康はもちろんのこと、「将来への影響」も無視できません。
その一つが、低身長です。通常、身長が急激に伸びる「成長スパート」と呼ばれる時期は、男子が13歳前後なのに対し、女子は11歳前後。伸びが止まるのも早く、16歳ごろには骨端線(骨の端にある成長点)が閉じます。10代前半までは伸び盛りで、この大事な時期に低栄養状態が続くと本来伸びるはずだった分が伸びなくなってしまうのです。
また、女の子は、8歳くらいから体の成長の変化が始まります。女性ホルモンの分泌量が増え、乳房の発達など第2次性徴が出現し、初潮を迎え、妊娠や出産が可能な体へと変わっていきます。この時期の栄養不足は無月経や無排卵などを引き起こし、将来妊娠しにくくなることもあります。適切な時期に十分な量のホルモンが分泌されないことで、骨粗鬆(こつそしょう)症になったり、更年期障害の症状がひどくなったり、生涯にわたって影響を及ぼすことも少なくありません。
河合医師はこう話します。
「子どもたちの多くは『今、やせたい』『足が細くなりたい』ということだけで、将来、背が伸びなくなるとか、赤ちゃんができにくくなることまでは考えが及んでいません。どんな人生を選ぶかはもちろん本人の自由なのですが、自分が望む人生の可能性を狭めてしまうリスクがあることを、本人にも親にも知っておいてほしいと僕は思っています」
(取材・文/熊谷わこ)