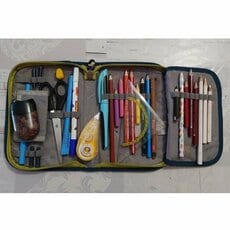謎解きクリエーターとして大活躍の松丸亮吾さん。自由研究の思い出や、やる気を引き出してくれた親の声かけについて話してくれました。子育て情報誌「AERA with Kids 2025年夏号」(朝日新聞出版)から紹介します。
【図】松丸亮吾さんの小学校時代の自由研究テーマはこちら子どものモチベーションを高めてくれた親の質問力
小学3年生ごろだったかな。夏休み、家の前に大きなアリの巣を見つけたんです。巣の近くに砂糖を置いてみたら、ぶわーっとアリたちが集まってきて、巣まで運んでいく。そこで、砂糖を巣から少しずつ離していって、どのくらい先までアリが認知できるのか観察し、自由研究にまとめました。
別の年には、ポケモンに登場するキャラクターの“技のダメージ”を計算式で表しました。「この場面ではこの技の威力が上がる」と分析するのは楽しかったですね。
「コラッツ予想」という数学の未解決問題を取り上げたこともあります。「正の整数を、偶数なら2で割って、奇数なら3倍して1を足すという操作を繰り返すと、どんな数でも必ず1に到達する」というもので、これまで多くの学者をとりこにしてきた、不思議で奥深い問題なんです。
僕は小さいころから、やらされることや押し付けられることが苦手で、自由研究のテーマも自分で決めていました。“自由”と名のつく研究なんですから、好きなことを突き詰めるほうが楽しい。
とはいえ、夏休みの宿題は毎年極限まで放置するタイプ(笑)。すると、親が「自由研究、どんなことするの?」とさりげなく質問してくるんです。「決めてない」というと、「最近は何に興味あるの?」と。会話を重ねるうちに、気づいたら方向性が決まっているということもありました。
「早くやりなさい」と強制されていたら、とたんにやる気を失っていたと思います。子どもの話を「うんうん」と聞きながら、うまく考えを引き出してくれる伴走者のような両親でした。何か質問をしても“答え”を教えるのではなく、検索の仕方や調べるコツなど、“答えを導くハウツー”を教えてくれた。おかげで、自分で答えにたどりつく力がついたと思っています。
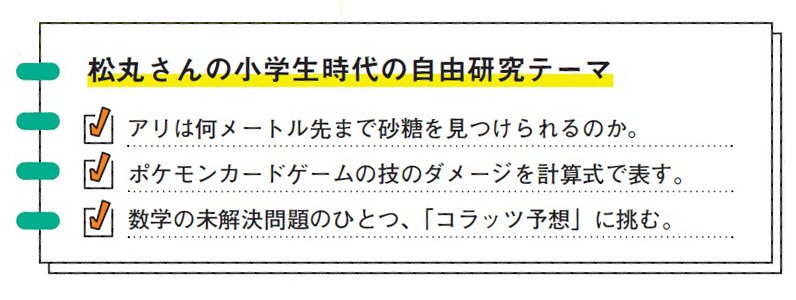
ゲーマーだった小学生時代 兄に勝つために考え抜いた
子ども時代は筋金入りのゲーマーでした。1日1時間までと時間制限をされても、ゲーム機を没収されても、決して勉強に向かう子どもではなかった。両親はついに折れ、「勉強を1日2時間したらいくらでもゲームしていい」という方針になりました(笑)。
次のページへこれからの時代に必要な力とは?